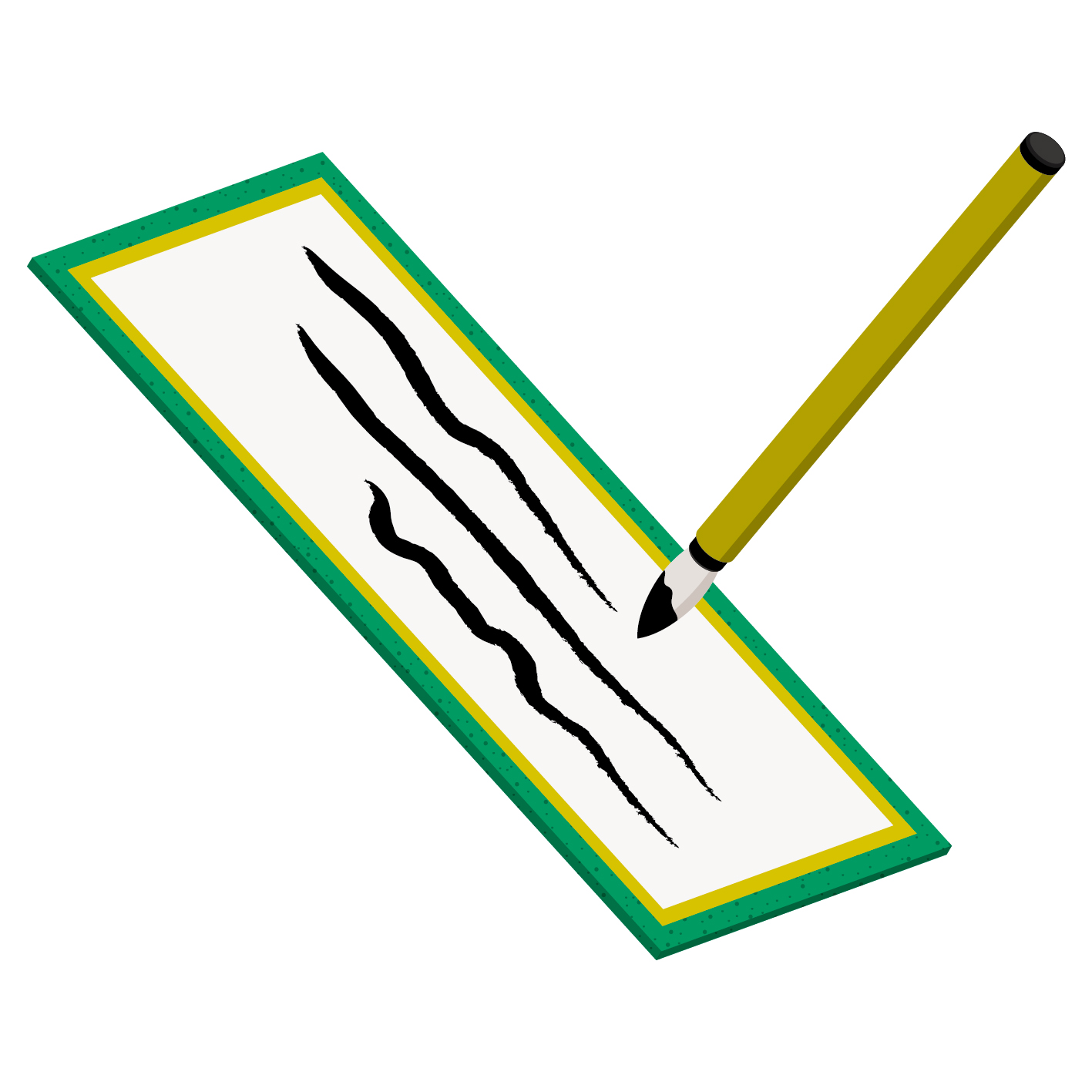俳句ってむずかしそう…と思っていませんか?実は俳句は、中学生でもかんたんに楽しめる日本の伝統文化なんです。たった17音の言葉で、季節や気持ちを表現できるって、ちょっとすごくないですか?
この記事では、俳句の基本から季語の使い方、カンタンな作り方、よくある失敗の直し方、そして実際の中学生の作品例まで、ぜんぶわかりやすく紹介します。学校の宿題やコンクールにも役立つ内容ばかりなので、ぜひ最後まで読んで、自分だけの一句をつくってみましょう!
\お買い物マラソン開催情報/ 楽天ランキングページはこちら<PR>
俳句ってなに?中学生にもわかる俳句の基本と魅力
俳句の定義と特徴を知ろう
俳句(はいく)とは、日本で生まれたとても短い詩のことです。たった17音、つまり「五・七・五」の三つのリズムだけでつくる文芸で、世界中でも珍しいほど短い詩です。でも、この短さの中に、自然や季節、感情や出来事などをぎゅっと詰め込めるのが、俳句の魅力です。
俳句にはふつう「季語(きご)」と呼ばれる季節を表す言葉が入っており、その言葉から季節感や情景を読者に伝えます。また、最後に「切れ字(きれじ)」という、句を引きしめる言葉が使われることもあります(たとえば「や」「けり」「かな」など)。
このように、少ない言葉でたくさんの意味を込める俳句は、「言葉のアート」とも言えるでしょう。
なぜ「五・七・五」なの?リズムの秘密
俳句は「五・七・五」というリズムで作られています。これは、全部で17音(おん)を使うという意味で、実際の文字数ではなく、音の数を数えます。たとえば「さくらさく」という言葉は、「さ・く・ら・さ・く」の5音です。
この「五・七・五」のリズムは、日本語の話し方にとてもなじんでいて、読むと自然なテンポになります。昔から日本人の耳に気持ちよく響くこのリズムが、俳句という表現方法にぴったりだったのです。
また、音の数が限られているからこそ、言葉を選ぶ力や想像力が大切になります。短いからこそ深い。これが俳句のすごさでもあります。
俳句と短歌の違いはなに?
俳句とよく似た日本の詩に「短歌(たんか)」があります。どちらも日本の伝統的な詩ですが、大きな違いがあります。
俳句は「五・七・五」の17音でできているのに対し、短歌は「五・七・五・七・七」の31音でできています。つまり、短歌の方がもっと長いです。そのため、短歌は気持ちや情景をより詳しく表現することができます。
また、俳句はふつう「季語」が必要ですが、短歌には季語の決まりはありません。自由に言いたいことを書けるのが短歌の特徴です。
俳句は、短くてシンプルな分、読み手の想像にまかせるところが多く、読む人によって感じ方が変わるのも面白いところです。
俳句にこめる「こころ」とは?
俳句を作るときに大事なのは、「気持ち」や「心の動き」を込めることです。何かを見て「きれいだな」「おもしろいな」「さびしいな」と感じた気持ちを、そのまま俳句に入れると、読む人の心にも伝わりやすくなります。
たとえば、「さくらがさく」だけでは事実を伝えているだけ。でも、「さくらさく 卒業アルバム 閉じながら」とすると、春の桜と卒業の切なさが伝わってきますよね。
大事なのは、「上手に作ること」よりも「自分の感じたことを素直に言葉にすること」です。言葉に気持ちがこもっていれば、それは立派な俳句です。
有名な俳句を読んでみよう
ここで、有名な俳句をいくつか紹介します。どれも短いけれど、とても印象に残る名句ばかりです。
| 作者 | 俳句 | 意味や感じること |
|---|---|---|
| 松尾芭蕉 | 古池や 蛙飛びこむ 水の音 | 静けさの中に、カエルが飛び込んだ音がひびく |
| 与謝蕪村 | 春の海 ひねもすのたり のたりかな | 春の海が一日中ゆったりとゆれている様子 |
| 小林一茶 | やせ蛙 まけるな一茶 これにあり | 一茶が弱いカエルを応援しているユーモラスな句 |
このように、有名な俳人たちも身近な自然や小さな気持ちを大切にして、素晴らしい俳句を生み出しています。
季語ってなに?俳句に必要な理由とその役割
「季語」は季節をあらわす言葉
俳句には「季語(きご)」という言葉を入れるのが決まりです。季語とは、春・夏・秋・冬の四季をあらわす言葉のことで、自然の風景や年中行事、動物や植物などがふくまれます。たとえば、春の季語には「さくら」「つばめ」「卒業」などがあり、夏なら「かぶと虫」「入道雲」「花火」などがあります。
季語を入れることで、その俳句がどの季節の情景をうたっているのかが、すぐにわかるようになります。また、読む人にとっても、共通のイメージが浮かびやすくなります。季語は、俳句の中で季節の空気や気持ちを感じさせる大切な言葉なのです。
なぜ俳句に季語が必要なの?
俳句に季語を入れる理由は、読んだ人がすぐに情景を思い浮かべられるようにするためです。たった17音の中で、どんな季節なのか、どんな場面なのかをすばやく伝えるには、共通の季語を使うのがとても効果的なのです。
たとえば、「かき氷」と聞けば、夏の暑い日を思い出しますよね?「紅葉(もみじ)」なら秋、「雪だるま」なら冬というように、季語は読む人の頭の中にその季節の絵を浮かばせてくれます。
また、俳句は昔から「自然をよみ、人のこころをうつす詩」と言われています。自然と心は切っても切れないもの。そのため、季語を使って季節を感じながら気持ちを表すことが、俳句の伝統として大切にされているのです。
四季ごとの代表的な季語一覧
季語には、季節ごとに多くの種類があります。ここでは中学生にもわかりやすい、身近な季語を表にまとめてみましょう。
| 季節 | 季語の例 |
|---|---|
| 春 | 桜、たんぽぽ、卒業、入学、つばめ |
| 夏 | かき氷、海、花火、金魚、セミ |
| 秋 | もみじ、月見、どんぐり、運動会、稲刈り |
| 冬 | 雪、こたつ、クリスマス、みかん、雪だるま |
このように、学校行事や自然、食べ物まで、さまざまな言葉が季語として使われています。俳句を作るときに、この表を見ながら季語を探すと、楽しく作れるはずです。
季語辞典を使ってみよう!
俳句を作るときに「どんな季語があるのかな?」と困ったときは、「季語辞典(きごじてん)」を使ってみましょう。インターネットでも「子ども向け季語辞典」などが公開されており、検索もかんたんです。
たとえば、「春 季語」「秋 季語」などと調べると、季語が一覧で出てきます。また、季語辞典には、季語の意味や使い方も書かれているので、とても便利です。
学校の図書室や図書館にも置いてあることが多いので、手にとって見てみるのもおすすめです。
季語を探しているうちに「この言葉、面白いな」「この季語、使ってみたいな」という発見があり、それが俳句づくりのヒントになることもありますよ。
季語を入れる位置と使い方のコツ
季語は俳句の中に必ず入れますが、入れる場所には決まりはありません。「五・七・五」のどこに入れても大丈夫です。ただし、自然な流れで読めるようにすることが大事です。
たとえば「春の海 ゆれる小舟と 猫の声」では「春の海」が季語で、はじめに入っています。このように最初に季語を入れると、読む人がすぐに季節をイメージしやすくなります。
また、「季語っぽい言葉」ではなく、本当に季語として認められている言葉を使うのがコツです。「友だち」や「スマホ」などは季節感がないため、俳句の中では季語になりません。
自然や季節を感じられる言葉を大切にして、自分だけの一句を作ってみましょう。
中学生向け!俳句のカンタンな作り方ステップ5
テーマを決めるところから始めよう
俳句を作るとき、まず最初にすることは「テーマを決める」ことです。テーマとは「どんなことを書きたいか」「どんな気持ちを伝えたいか」をはっきりさせることです。
たとえば、「夏休みの思い出を書きたい」「運動会で走ったときの気持ちを詠みたい」「桜を見てきれいだと思った」など、自分が心に残っていることや印象に残った出来事をテーマにすると作りやすいです。
また、俳句は短いので、ひとつのテーマにしぼるのがコツです。「花火」と「海」と「スイカ」など、いくつも入れようとすると、ごちゃごちゃして伝わりづらくなります。「花火」なら花火だけに集中して、そのときの音、色、気持ちなどをしっかり描くようにしましょう。
まずは、自分の身の回りにある「季節を感じるできごと」に目を向けてみてください。
五・七・五の形にあてはめよう
テーマが決まったら、いよいよ言葉を「五・七・五」のリズムに合わせて並べていきます。ここで大切なのは、「文字の数」ではなく「音の数」を数えることです。
たとえば「さくら」は2文字ですが、音は「さ・く・ら」の3音です。正しく数えながら言葉を並べていきましょう。
最初は、音を数えるのが難しいかもしれませんが、声に出して読んでみると自然にリズムが分かってきます。
「たのしいな(5音)」「ともだちといる(7音)」「春のひる(5音)」のように、音の数にぴったり合うように言葉を調整します。長すぎたら短くする、短すぎたら言葉を足すなどしてバランスを整えましょう。
音のリズムが合ってくると、読んでいてとても気持ちのいい俳句になります。
季語をどこに入れるか考えよう
俳句には季語を入れることが大切です。テーマに合った季語を選び、それをどこに入れるかを考えましょう。
たとえば「さくら」「雪」「セミ」「月見」など、選んだテーマにぴったりな季語があるか、季語辞典やインターネットで探してみましょう。
季語はどの位置に入れてもOKですが、最初に入れるとその後の言葉が自然につながりやすくなります。「さくら咲く 道を歩いて 思い出す」などのように、最初に季語を使うと季節感がすぐに伝わります。
また、季語を入れることで「この句は春のことを言っているんだな」と、読む人に伝える力がぐんと強くなります。
もしうまく入らないときは、言葉を少し変えてみたり、他の季語に変えてみたりするのもひとつの手です。
言葉の響きやリズムを整えよう
言葉を並べたら、次にやることは「響き」や「リズム」を整えることです。俳句は音の美しさも大切にする詩なので、声に出して読んでみて、耳に心地よいかどうかを確認しましょう。
たとえば、「にじがでた あさのそらには ひこうきぐも」と作ったとき、リズムがスムーズで、イメージもすっと浮かびますよね。これが理想的な形です。
逆に、「朝に虹 空を飛ぶ飛行機 気持ちいい」では、音数がバラバラだったり、リズムが不自然だったりして、俳句としては整っていません。
また、「同じ音が続きすぎていないか」「言葉が重たすぎないか」などにも注意して、スッキリした響きになるように意識すると、ぐっとレベルアップします。
出来上がったら声に出して読んでみよう
俳句が完成したら、必ず声に出して読んでみましょう。目だけで読むのと、耳で聞くのとでは印象が全く違います。
声に出すことで、リズムの良し悪しや、言葉のつながりの自然さが分かりやすくなります。もし読んでいて「なんか言いにくいな」「言葉がつっかえるな」と思ったら、そこが見直しポイントです。
また、家族や友達、先生などに読んでもらうと、自分では気づかなかった感想がもらえて勉強になります。「この言葉いいね!」とか「ここ、もう少し短いともっとスッキリするかも」といった意見を聞くのも、上達の近道です。
俳句は作って終わりではありません。読んでもらって、感じてもらって、伝わってこそ本当の俳句です。自信をもって声に出してみましょう!
俳句作りでよくある失敗とその直し方
季語を忘れてしまった!どうする?
俳句を作っていると、テーマや言葉選びに夢中になって、つい「季語」を入れるのを忘れてしまうことがあります。でも大丈夫!そんなときはまず、自分の句をよく読み返して、「どの季節のことを言いたかったのか?」を思い出してみましょう。
たとえば、「昼休み 風と遊んだ 空のした」という句を作ったとします。ここには季語が入っていません。でも「風」が出てきているので、もしこれが春の風をイメージしているなら、「春風(はるかぜ)」という季語に言いかえることで、春らしさがしっかり伝わるようになります。
つまり、「昼休み 春風と遊ぶ 空のした」と直せば、立派な俳句になります。
季語を忘れても、あとから付け足す・言葉を入れかえることで、自然に季節感を出せるので、あきらめずに工夫してみましょう。
意味が伝わらない俳句になったときは?
ときどき、「自分ではわかるけど、読んだ人には意味が伝わりにくい俳句」になってしまうことがあります。そういうときは、「自分がその句にこめた気持ちが、ちゃんと言葉に出ているか?」を見直してみましょう。
たとえば、「空へとぶ ひとつの音に こたえる目」だけを読むと、何を表現したいのか少し分かりにくいですね。けれど、これがもし「花火を見上げたときの感動」なら、「花火」「夜空」「ひかり」など、より具体的な言葉を入れることで、情景や気持ちがはっきり伝わるようになります。
「伝わるかどうか」を判断するには、家族や友達に読んでもらうのもおすすめです。「この句、どう思う?」と聞いてみると、思わぬ気づきが得られますよ。
5・7・5になっていない!調整の方法
俳句は「五・七・五」の17音で作るのが基本です。ですが、最初に言いたいことを考えてから言葉を並べると、どうしても音の数が合わなくなることがあります。
そんなときは、言葉を短くしたり、同じ意味の別の言い方に変えたりして、音数をぴったりに調整しましょう。
たとえば、「かぜがふく きょうの放課後 さむかった」は音数が「5・7・6」になってしまっているので、これを「風がふく 放課後の道 さむい空」などと直せば「5・7・5」におさまります。
言い方を少し変えるだけで、リズムが整って読みやすくなります。五・七・五のリズムは日本語にとてもなじんでいるので、声に出して気持ちよく読める形を目指しましょう。
説明っぽくなってしまうときの工夫
俳句を作ると、「〇〇が〇〇でした」という説明のような文になってしまうことがあります。たとえば、「今日は暑かった 風がなかった つかれました」では、事実を伝えているだけで、詩としての面白さや情景が伝わりません。
そんなときは、「見たこと」「聞こえたこと」「感じたこと」を表す言葉に変えてみるのがコツです。たとえば、「まぶしさに 立ち止まる道 夏の午後」とすると、暑さが伝わってきて、読んだ人の心にイメージが浮かびます。
説明ではなく、心に残る「場面」を描くようにすると、俳句らしい表現になります。感情や風景をうまく言葉にする練習をしていきましょう。
どうしても思いつかないときのヒント
「何を書こうかな?」と、ぜんぜん思いつかないときもあります。そんなときは、まず「今日の出来事」を思い出してみましょう。
学校であったこと、外で見た景色、友だちとの会話…日常の中には俳句のタネがたくさんあります。
また、「季語」からスタートするのもおすすめです。たとえば「雪」「桜」「入道雲」など、気になる季語を一つ決めて、「それを見たときにどんな気持ちだったか」を考えてみましょう。
さらに、新聞や写真、絵本などからインスピレーションを得るのも有効です。ひとつの言葉や絵から想像をふくらませることで、素敵な一句が生まれることもあります。
大切なのは「完璧な句を作ろう」と思いすぎず、「言葉あそび」のような気持ちで楽しむことです。
実践編!中学生が作った俳句の例と先生のアドバイス
春の俳句例とワンポイントアドバイス
俳句例:
さくら舞う 校庭に残る 足あとよ
この俳句は「春」と「卒業」をテーマにした一句です。季語である「さくら」が使われており、春の情景と共に、別れのさみしさがにじみ出ています。「校庭に残る足あと」という表現が、時間の流れや思い出を感じさせてとても上手です。
アドバイス:
この句のように、「花が咲いた」「春になった」などの直接的な表現よりも、「足あと」や「舞う」という動作や物に感情を込めることで、読み手の想像を広げることができます。物語を感じさせる俳句を作るのが上達への近道です。
夏の俳句例とワンポイントアドバイス
俳句例:
昼下がり セミのこえだけ ひびく道
こちらは夏の定番、「セミ」を使った句です。季語は「セミ」で、「昼下がり」という時間の言葉と「ひびく道」という描写から、夏の暑さと静けさがよく伝わってきます。音に注目した点も素晴らしいですね。
アドバイス:
夏は暑さやにぎやかさを感じやすい季節なので、音(セミ、風鈴、花火など)やにおい(スイカ、汗など)など五感を使った表現を意識すると、より臨場感のある俳句になります。できるだけ「感じたこと」を表すのがポイントです。
秋の俳句例とワンポイントアドバイス
俳句例:
月あかり ランドセルにも 色うつす
この句は秋の夜の情景を描いています。季語は「月あかり」で、秋の静かで澄んだ空気が感じられます。「ランドセル」に月の光が当たるという発想が面白く、日常と自然の調和が表現されています。
アドバイス:
秋は「月」「紅葉」「虫の声」など、しずかで物思いにふけるような言葉が似合います。学校生活や自分の身の回りと組み合わせて俳句を作ると、読む人にとっても共感しやすくなりますよ。
冬の俳句例とワンポイントアドバイス
俳句例:
こたつ出す あしの取り合い 家族かな
こちらは冬の家庭のほっこりした光景を詠んだ句です。「こたつ」が季語で、寒い冬ならではの風景です。「足の取り合い」というリアルな場面がとてもおもしろく、読む人の顔が思わずゆるむような俳句です。
アドバイス:
冬は寒さだけでなく、家の中のぬくもりをテーマにすると、読む人に温かい気持ちを届けることができます。笑いやユーモアをまじえるのも、俳句の魅力のひとつです。
学校の俳句コンクールに向けたアドバイス
学校の俳句コンクールでは、「自分らしさ」がとても大切です。たとえば、上手な言葉よりも、「その人が実際に体験したこと」「感じた気持ち」が込められている句のほうが、先生や審査員の心に響きます。
また、季語を使っても、それだけで季節感が伝わらないこともあります。風景・気持ち・動作をうまく組み合わせて、ひとつの「場面」を描くようにしてみましょう。
さらに、他の人の俳句もたくさん読んでみることが大切です。「こんな表現があるんだ!」という発見が、自分の俳句のヒントになります。楽しみながら、自分だけの一句を生み出してみてくださいね!
まとめ
俳句は、たった17音の短い詩ですが、その中には季節の空気や自分の気持ちをたっぷり込める、とても奥深い日本の伝統文化です。今回紹介したように、中学生でもテーマを決めて、季語を選んで、五・七・五に整えていけば、しっかり俳句を作ることができます。
失敗しても大丈夫。言葉を直して、自分の思いがしっかり伝わる一句になるまで、何度でもチャレンジできます。そして大切なのは、「上手に作ること」ではなく、「感じたことをことばにしてみること」です。
俳句を通して、日本の四季をもっと好きになったり、自分の感性を発見したりすることができます。ぜひ、あなただけの俳句を楽しんでくださいね!