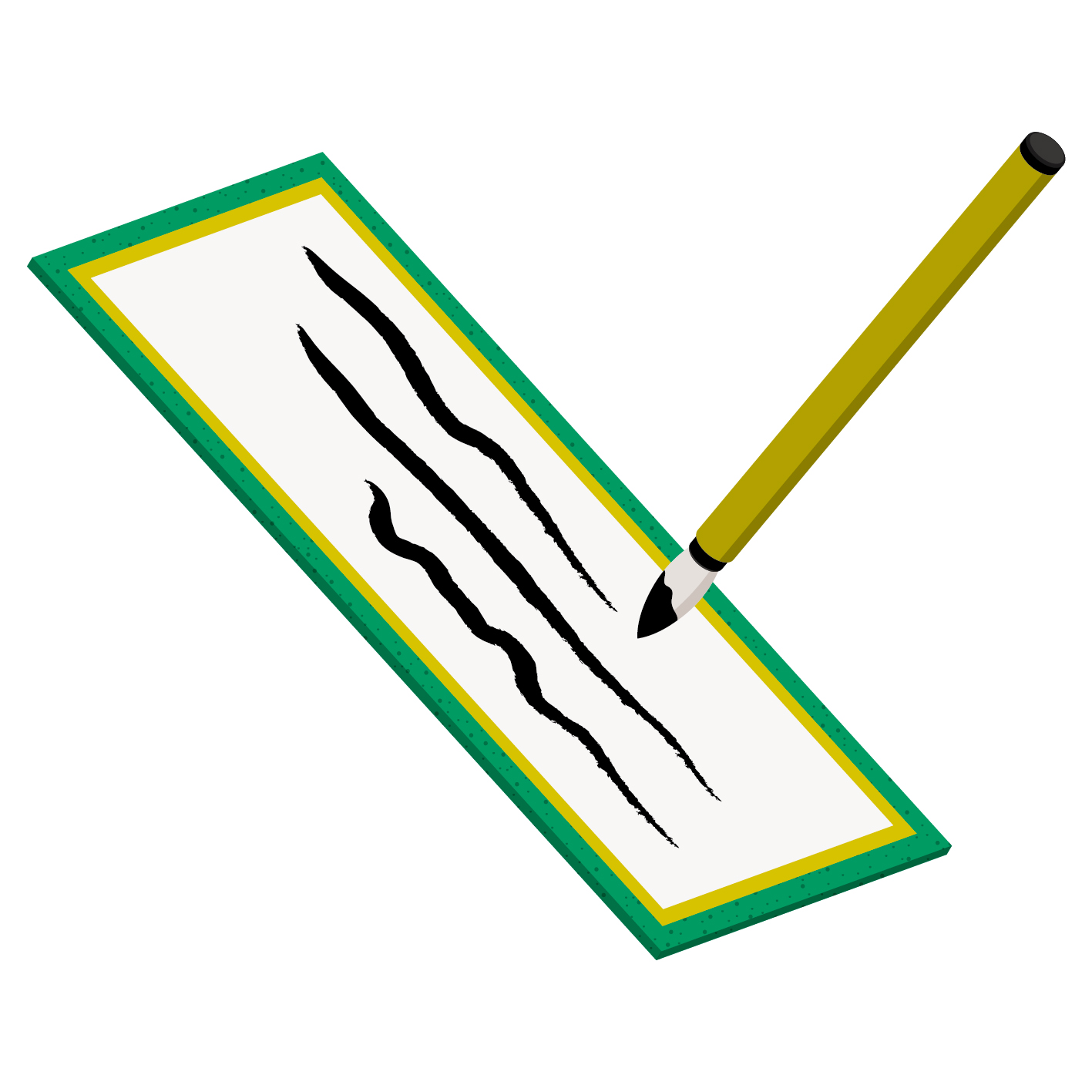俳句ってむずかしそう……と思っていませんか?
実は、たった17音のリズムに季語を入れるだけで、だれでも簡単に作れる楽しい表現なんです!
この記事では、小学生でも楽しく学べる「季語の一覧」と「俳句の作り方」をやさしく紹介します。春・夏・秋・冬の季節ごとにぴったりの季語や、俳句をまとめるノートの工夫、さらに楽しく遊べるアプリや本の情報までたっぷり掲載!自由研究や家庭学習、親子での活動にもおすすめの内容です♪
\お買い物マラソン開催情報/ 楽天ランキングページはこちら<PR>
四季を感じよう!春・夏・秋・冬の季語をやさしく紹介
春の季語ってなに?小学生に人気の例を紹介
春は新しい生活が始まる季節。ぽかぽかした日ざしや、花が咲く景色を思い浮かべる人も多いですね。俳句における「季語」とは、その季節をあらわす特別な言葉のことです。春の季語には、自然や行事、動物などがたくさんあります。たとえば「さくら」「つくし」「入学」「春風」などが春の代表的な季語です。
小学生に人気のある春の季語をいくつか紹介します。
-
さくら:春を代表する花。満開の景色はとてもきれいです。
-
つくし:春になると野原に生える小さな植物。
-
入学:新しい学校生活が始まるドキドキの季語。
-
ひなまつり:3月3日の行事。女の子のお祝いの日です。
-
春風:あたたかくてやさしい風。心がほっとします。
こうした季語を使って、自分だけの春の俳句を作ってみると、自然や日々の出来事に目が向いて、楽しい発見があるはずです。
夏の季語を探そう!身近なものがたくさん
夏はあつ〜い日が続きますが、楽しい行事もいっぱいありますよね。夏の季語には、海や空、虫たち、夏祭りなど、身近なものが多く含まれます。たとえば「かぶとむし」「スイカ」「花火」「あさがお」などが人気の夏の季語です。
以下に、小学生におすすめの夏の季語をいくつか紹介します。
-
あさがお:夏休みの観察日記でもおなじみのお花。
-
かぶとむし:夏の森でよく見かける虫の王様。
-
スイカ:冷たくてあま〜い夏の味。
-
花火:夜空をカラフルにする夏のイベント。
-
セミ:夏の朝に大きな声で鳴いている虫。
夏の季語は元気いっぱいな言葉が多く、俳句を作るのがとても楽しくなります。夏休みに自由研究として俳句にチャレンジするのもいいですね。
秋の季語でしっとり俳句を作ってみよう
秋はすこし肌寒くなってきて、葉っぱが色づき、食べものがおいしくなる季節です。俳句の世界でも、秋の季語は「しっとり」「もの思いにふける」といった静かな気持ちを表すものが多いです。たとえば「もみじ」「とんぼ」「月」「いなほ」などがあります。
小学生にぴったりの秋の季語をいくつか紹介します。
-
もみじ:赤や黄色に色づく葉っぱ。秋の代表です。
-
とんぼ:空をすいすい飛んでいる小さな虫。
-
月:中秋の名月など、秋の夜にぴったり。
-
いなほ:稲の実がたくさんついた様子。秋の田んぼに多く見られます。
-
さつまいも:焼きいもにして食べたくなる秋の味。
秋の俳句は、落ちついた気持ちで季節を感じながら作ることができるので、感性を育てるのにぴったりです。
冬の季語で感じる寒さとあたたかさ
冬は寒くて雪が降る季節。でも、その分、こたつやおでん、クリスマスなど、あたたかい楽しみもたくさんあります。俳句に使われる冬の季語も、寒さとぬくもりがまざったような魅力があります。
小学生におすすめの冬の季語はこちらです。
-
ゆき:ふんわりと白い雪。冬らしさの象徴です。
-
こたつ:ぬくぬくあたたかい冬のアイテム。
-
おでん:体がぽかぽかになる食べもの。
-
クリスマス:12月の大きなイベント。
-
しもばしら:寒い朝に見られる氷の柱。自然の芸術です。
冬の俳句は、寒さを感じながらも、心のあたたかさを表現することができるので、家族や友だちに読んでもらうととても喜ばれます。
いつでも使える!季節を問わない便利な季語
実は、俳句には「通年(つうねん)」使える季語もあります。これはどの季節でも使える言葉で、特定の季節にしばられずに俳句を作りたいときに便利です。小学生が使いやすい通年の季語には、気持ちや自然の様子を表す言葉が多くあります。
-
風:季節にかかわらずいつでも吹いています。
-
星:一年中、夜空に光っています。
-
花火:夏以外にもイベントで使われることがあります。
-
虫の声:種類によっては秋だけでなく春にも聞こえます。
-
夢:子どもがよく見る、楽しい空想の世界。
通年の季語を使うと、季節感にとらわれない自由な発想で俳句を作ることができるので、初めての俳句作りにもぴったりです。
小学生でも簡単!季語を使った俳句の作り方
俳句ってなに?五・七・五のリズムを覚えよう
俳句(はいく)は、世界でいちばん短い詩(し)と言われていて、日本の伝統的な文学のひとつです。俳句の大きなルールはたった2つ。五・七・五の17音で作ることと、季語(きご)を入れることです。この「五・七・五」というのは、1行目が5音、2行目が7音、3行目が5音というリズムのことをいいます。
たとえば、こんな俳句があります。
さくらさく(5)
にわにちょうちょが(7)
とんできた(5)
このように、五・七・五のリズムで言葉を並べるだけで、立派な俳句になります。短い言葉の中で、季節や気持ちを表すことが大切です。
難しそうに見えるかもしれませんが、まずは「音を数える」「季語を1つ入れる」という2つのポイントをおさえれば大丈夫!俳句をゲームのように楽しんで作っていきましょう。
季語はどこに入れたらいいの?ルールを覚えよう
俳句のルールの中で、とても大事なのが「季語を入れること」です。でも、「季語ってどこに入れればいいの?」と迷ってしまう人も多いはず。実は、季語を入れる場所に決まりはありません。どこに入れても大丈夫です。
たとえば、以下のような例を見てみましょう。
-
【先頭に入れる】
さくらちる しずかなみちを あるいてく
-
【真ん中に入れる】
やまのぼり あせをぬぐえば せみのこえ
-
【最後に入れる】
ゆきのなか ゆっくりはしる けいとらが
このように、俳句の中に季語が入っていればOKなんです。ただし、季語は1つだけにするのが一般的。たくさん入れると、どの季節を表したいのか分からなくなってしまうからです。
季語の位置を変えるだけで、俳句の雰囲気も変わってくるので、いろいろな場所で試してみるのも楽しいですよ。
季語から想像をふくらませてみよう
俳句を作るときには、「季語からイメージをふくらませる」のがコツです。たとえば、「ゆき(雪)」という季語があったとしましょう。雪と聞いて、どんなことを思い浮かべますか?
-
まっ白な風景
-
ふわふわ舞いおりる雪のけむり
-
雪だるまを作る子どもたち
-
雪合戦でびしょぬれになった服
-
あたたかいこたつとミカン
このように、季語から頭の中に「絵」を思い浮かべて、それを言葉であらわすと俳句が作りやすくなります。ポイントは、五感(目・耳・鼻・口・手)をつかって想像することです。
たとえば、「風」という季語があったら「音」「におい」「肌にふれる感じ」「木がゆれる様子」など、いろんな視点で考えてみましょう。
こうすることで、オリジナリティのある俳句がどんどん生まれます!
まねして作ってみよう!簡単な俳句例
いきなり自分で俳句を作るのがむずかしいと思ったら、まずは「まねして作る」のがおすすめです。ここでは、小学生がまねしやすいシンプルな俳句を紹介します。
春の俳句
さくらさく おかあさんと はなみする
夏の俳句
あさがおが きれいにさいて おはようと
秋の俳句
いちょうのき きいろくそまる みちのした
冬の俳句
ゆきがふる しずかなまちに こえひびく
こういった俳句の「リズム」や「言葉の使い方」をまねして、自分なりにアレンジするだけで、立派なオリジナル俳句が完成します。
最初は恥ずかしがらずに、たくさんまねして、言葉を楽しむ気持ちを大切にしましょう!
友だちや家族と俳句を作って遊ぼう
俳句はひとりで作っても楽しいですが、友だちや家族と一緒に作るともっと楽しくなります!
たとえば、こんな遊び方があります。
-
テーマを決めてみんなで一句ずつ作る(例:「夏」「動物」「学校」など)
-
しりとり俳句:1人が作った俳句の最後の言葉を使って次の人が俳句を作る
-
俳句バトル:どっちの句がいいか投票して遊ぶ
-
絵を描いてその絵から俳句を作る
家族でごはんの時間に一句発表し合う「俳句タイム」を作っても面白いですよ。
人と一緒に作ることで、いろいろな感じ方や表現に出会えて、語彙(ごい)も増えていきます。
俳句に使える!小学生にぴったりの季語一覧100
春の季語20選(意味つき)
春は、生命が目を覚ます季節。花が咲き、虫が出てきて、あたたかい風がふいてきます。そんな春の気持ちを表す季語を、意味といっしょに紹介します。
| 季語 | 意味・説明 |
|---|---|
| さくら | 春の代表的な花。満開の景色はおなじみ。 |
| つくし | 野原に出てくる細長い植物。 |
| 入学 | 新しい学年・学校が始まるとき。 |
| 春風 | あたたかくて気持ちのよい風。 |
| ひなまつり | 女の子の成長を祝う行事(3月3日)。 |
| ふきのとう | 春に最初に出てくる山菜の一種。 |
| ちょうちょ | 春によく飛ぶ、カラフルな虫。 |
| すみれ | 春に咲く、小さくてかわいい花。 |
| はるかぜ | 春のやさしい風(春風と同じ)。 |
| さんぽ | 春のあたたかい日に歩くのが楽しい。 |
| こいのぼり | こどもの日(5月5日)に飾る旗。 |
| やよい | 旧暦の3月を表す春の言葉。 |
| さくらもち | 桜の葉で包んだ春のおかし。 |
| たんぽぽ | 道ばたや公園によくある黄色い花。 |
| わかば | 新しく出たばかりの若い葉っぱ。 |
| にゅうがくしき | 学校で新1年生をむかえる行事。 |
| ぴかぴかのランドセル | 新しい気持ちを表すイメージ季語。 |
| ひなたぼっこ | あたたかい日に日光を楽しむこと。 |
| はるのにおい | 春の空気にふくまれる草や花のにおい。 |
| はるのひざし | やわらかくてまぶしい春の太陽の光。 |
春の季語は、明るくてやさしい気持ちになれる言葉が多いです。春の自然や行事を思い出しながら俳句を作ってみましょう。
夏の季語20選(意味つき)
夏は元気いっぱいの季節。虫が鳴き、草が伸び、空は高くて青いです。夏休みやお祭りなど、ワクワクすることがいっぱい!
| 季語 | 意味・説明 |
|---|---|
| あさがお | 夏の観察で育てる人気の花。 |
| かぶとむし | 夏の夜に出てくる人気の昆虫。 |
| セミ | 夏に大きな声で鳴く虫。 |
| スイカ | 夏の味といえばこれ! |
| 花火 | 夜空に広がる夏のイベント。 |
| なつやすみ | 学校が長いお休みに入る期間。 |
| プール | 水の中で遊べる楽しい場所。 |
| うみ | 夏に出かける定番スポット。 |
| かきごおり | 氷をけずってシロップをかけたおやつ。 |
| ほしぞら | 夏の夜にきれいに見える空。 |
| なつまつり | みこし・屋台・音楽がにぎやかな行事。 |
| ひまわり | 背が高くて太陽に向かって咲く大きな花。 |
| はだし | 地面の熱さを感じる夏の足もと。 |
| くも | 入道雲など、もくもくした夏らしい雲。 |
| なつのそら | 青くてひろい空、飛行機雲も出やすい。 |
| おにやんま | 大きくて速く飛ぶトンボ。 |
| せんぷうき | 風を送ってくれる夏の家電。 |
| すいかわり | スイカを棒で割る夏の遊び。 |
| びーちさんだる | 海で歩くためのくつ。 |
| きもだめし | 夜におばけ役が出てくる遊び。 |
夏の季語は楽しくてにぎやかな言葉がたくさん!元気な言葉でリズムよく俳句を作りましょう。
秋の季語20選(意味つき)
秋はしっとりした気持ちになる季節。葉っぱが赤や黄色にそまり、空気もひんやりしてきます。食べものがおいしくなるのも秋の楽しみ。
| 季語 | 意味・説明 |
|---|---|
| もみじ | 秋になると赤や黄色に色づく葉っぱ。 |
| いちょう | 黄色くなる大きな葉。 |
| とんぼ | 秋によく空を飛ぶ虫。 |
| つき | 中秋の名月など、夜空がきれいな季節。 |
| いなほ | 稲が実ってたれてくる様子。 |
| どんぐり | 公園などで見つかる茶色い実。 |
| きのこ | 森の中に生えるふしぎな植物。 |
| さつまいも | 秋になると焼きいもにして食べたくなる! |
| くり | とげとげの中にある茶色の実。 |
| しぐれ | 秋にふる、急に止む小雨。 |
| すすき | 風にゆれる細長い草。 |
| うろこぐも | 空にうろこのように並ぶ雲。 |
| こうよう | 木々の葉が赤や黄色に染まること。 |
| あきかぜ | 涼しくて気持ちのよい風。 |
| なし | 秋のくだもの。ジューシーで甘い。 |
| ぶどう | つぶつぶの実があまくておいしい。 |
| くさのにおい | ひんやりした草の香り。 |
| あきのそら | すじ雲や高い空が特徴的。 |
| こうようやま | 色づいた山の風景。 |
| あきのよる | 長くてしずかな夜。 |
秋は感性を育てるのにぴったりの季節です。静かな景色やおいしい食べものをテーマに俳句を作ってみましょう。
冬の季語20選(意味つき)
冬は寒いけれど、クリスマスやお正月など楽しい行事もあります。雪やこたつなど、心も体もあたたまる季語がいっぱい!
| 季語 | 意味・説明 |
|---|---|
| ゆき | 白くてふんわり、冬の代表的な風景。 |
| こたつ | 家の中であたたまるテーブル。 |
| おでん | 体があたたまる冬の食べもの。 |
| しもばしら | 朝の寒さでできる氷の柱。 |
| クリスマス | 冬の大きなイベント(12月25日)。 |
| おしょうがつ | 新しい年をむかえる日(1月1日)。 |
| みかん | こたつに合うあまい果物。 |
| せきがん | 寒さをあらわす言葉。 |
| なべりょうり | みんなで食べるあったかい料理。 |
| ふゆのそら | 青くてつめたい空。 |
| かぜ | 寒い日によくふく風。 |
| ふゆやすみ | 冬にある学校のお休み。 |
| しんしん | 雪が静かにふる様子。 |
| つらら | 氷がつららのようにたれさがる。 |
| たいこもち | お正月などで見る日本の伝統芸。 |
| ふとん | 寒い日にあったかくなる寝具。 |
| あられ | 小さくてかたい氷の粒。 |
| ふゆのにおい | 空気の中にあるキンとした冷たいにおい。 |
| しろいはくい | 雪の中にぴったりな白い衣。 |
| こおり | 水がこおってできたかたいかたまり。 |
冬は風景の中に詩(うた)がたくさんつまっている季節。冷たさとあたたかさを言葉で表現してみましょう。
通年使える季語20選(意味つき)
最後に、季節を問わずに使える便利な季語を紹介します。どんな季節でも俳句を作りたいときに役立ちます。
| 季語 | 意味・説明 |
|---|---|
| 風 | いつの季節にも感じられる自然の動き。 |
| 星 | 夜空に光る天体。季節に関係なく見える。 |
| 山 | 四季それぞれで見え方が変わる自然の風景。 |
| 雨 | 季節に関係なくふる自然の恵み。 |
| 夢 | どんな季節でも見る、心の中の出来事。 |
| 花 | いろんな季節に咲くため通年で使える。 |
| 水 | 自然や生活の中にある大切な存在。 |
| 空 | 毎日変わる色やかたちを見せる。 |
| 道 | 季節の中を歩く生活の一部。 |
| 声 | 人や動物の声、自然の音も含まれる。 |
| 音 | 通年で使える、耳で感じる要素。 |
| 光 | 太陽や月、星など、自然の輝き。 |
| 土 | 畑・田んぼ・道などにある自然の土。 |
| 花火 | 夏以外でもイベントで見られることあり。 |
| 笑顔 | 季節に関係なく大切な気持ち。 |
| 歌 | 季節を超えて楽しめる文化。 |
| 風船 | お祭りや誕生日など、通年で登場。 |
| 家 | 季節を感じる場所でもある。 |
| 朝 | 毎日のはじまり、どの季節にもある。 |
| 夜 | 季節の変化を感じられる時間帯。 |
学校や自由研究に使える!俳句のまとめノートの作り方
ノートに書くときのポイントは?
俳句を勉強したり、自分で作った俳句をまとめたりするときには、ノート作りがとても役立ちます。整理しながら書くことで、自分の成長も感じられて、自由研究としてもばっちり!
まず大切なのは、ノートを見やすく、楽しく書くことです。以下のようなポイントを意識してみましょう。
-
1ページに1つの俳句を書く(ごちゃごちゃしない)
-
季語を赤いペンや色鉛筆で目立たせる
-
書いた日付や場所を書くと、あとで見たときに思い出しやすい
-
自分の気持ちや作ったときのようすを一言そえる
-
間違いは消さずに、あとで見返せるように残すのもアリ!
季語とイラストをセットにして覚えよう
俳句ノートをもっと楽しくするコツは、「絵」をいっしょに描くことです。特に小学生にとっては、視覚的に季語を覚えるのがとても効果的。言葉だけでなく、イメージでも季節を感じられます。
たとえば、以下のようなイラストをかんたんに描いてみましょう。
-
🌸「さくら」 → ピンクの花びらと木
-
🐞「かぶとむし」 → ツノのある黒い虫
-
🍁「もみじ」 → 赤や黄色の葉っぱ
-
⛄「ゆき」 → ふわふわの雪だるま
-
🎇「花火」 → 夜空にパッとひらく火の花
色えんぴつやクレヨンを使って自由に描いてOKです!
さらに、季語ごとのコーナーを作って、辞書のようにまとめていくのもおすすめです。
自分だけの季語辞典を作ってみよう
たくさんの季語にふれたら、今度は**自分だけの「季語辞典」**を作ってみましょう!ノートやルーズリーフ、100円ショップの小さいファイルなどを使えば、かんたんに作れます。
作品発表ページも作ってみよう
俳句ノートを作ったら、ぜひ最後のほうに作品発表コーナーを作ってみましょう。お気に入りの俳句や、友だちや先生に見せたい俳句をまとめるページです。
こんなふうにデザインしても楽しいです:
-
表紙タイトル:「ぼく・わたしのベスト俳句」
-
金色やカラーペンでかざる
-
星マークをつけて「一番のお気に入り!」など評価をつける
-
友だちや家族からの感想を書いてもらうスペースを作る
作品発表のページがあると、「もっといい俳句を作りたい!」という気持ちも出てきて、自然に上達していきますよ。
ノート作りに便利な無料テンプレート紹介
最後に、俳句ノート作りに便利なテンプレートを活用する方法も紹介します。学校や家庭学習で使いやすいテンプレートは、以下のような内容が含まれています。
| テンプレート名 | 内容 |
|---|---|
| 俳句記録シート | 俳句・季語・意味・気持ちを書く欄付き |
| 季語辞典シート | 季語・イラスト・使った句をまとめる |
| 発表コーナー用 | ベスト句を飾るデザイン付き |
| 自由研究タイトルシート | 表紙に使えるデザイン入りテンプレ |
テンプレートは「小学生 俳句 ノート テンプレート」などで検索すれば、教育サイトや学習支援のページから無料でダウンロードできます。
印刷して使えば、俳句ノート作りがもっと楽しく、きれいに仕上がりますよ!
俳句をもっと楽しむ!おすすめの本・アプリ・イベント
小学生に人気の俳句の本3選
俳句をもっと知りたくなったら、やっぱり本がおすすめです。とくに、小学生でも読みやすく、イラストや例が豊富な本を選べば、楽しく学べます。ここでは、初心者向けの人気の俳句本を3冊紹介します。
① 『子どもと楽しむ 俳句歳時記(さいじき)』/角川学芸出版
-
春夏秋冬の季語がカラーの絵とともに紹介されていて、とても分かりやすい。
-
小学生の俳句例も多く、マネしやすい。
② 『小学生のための 俳句ドリル』/学研プラス
-
「五・七・五に当てはめてみよう!」と練習形式で学べる。
-
クイズ形式のページもあり、ゲーム感覚で楽しめる。
③ 『まんがでわかる俳句入門』/ポプラ社
-
まんがなので飽きずに読めて、キャラクターたちと一緒に俳句を学べる。
-
季語やリズム、表現のコツまでしっかり解説してくれる。
これらの本は、学校の図書館や地域の図書館にも置かれていることが多いので、まずは手に取ってみるのがおすすめです。
楽しく遊べる俳句アプリ紹介
今の時代は、スマホやタブレットでも俳句を楽しめる時代!
俳句をゲーム感覚で学べるアプリもあるので、移動中や空いた時間にぴったりです。
① 俳句てんてこまい(iOS/Android)
-
画面に出てくる季語や言葉を組み合わせて、自動で俳句を作るアプリ。
-
ランダムにできるので、おもしろい俳句がたくさん誕生する!
② ことばのパズル 俳句道場(iOS)
-
パズルを解きながら季語や言葉の意味を学べる。
-
難易度が選べるので、小学生でも安心。
③ はいくふうせん(iOS/Android)
-
ふうせんのように季語がぽんぽん出てくる!タップして俳句を完成させよう。
-
ビジュアルがカラフルで子ども向けに最適。
地域で開催されている俳句大会って?
実は、日本全国の多くの市町村や小学校では、子ども俳句大会や俳句コンテストが定期的に開催されています。こうした大会は、作品を応募するだけで参加できるものが多く、参加することで作文力や表現力を伸ばすチャンスにもなります。
-
地元の市役所や図書館でチラシが配られることもあり
-
「○○市 子ども俳句コンテスト」などと検索すると見つかる
-
入賞すると賞状や記念品がもらえることも!
また、**「全国こども俳句大会」**など、文部科学省や有名出版社が主催する大会もあります。応募は無料のことが多いので、ぜひチャレンジしてみましょう!
有名な俳人の俳句を見てみよう
俳句には歴史があり、昔の有名な俳人(はいじん)たちが残した句を読むことで、俳句の深さを感じることができます。
小学生にわかりやすい俳人と俳句をいくつか紹介します。
松尾芭蕉(まつお ばしょう)
古池や かわずとびこむ 水の音
→ 静かな池にカエルが飛びこんだ音。とても有名な一句です。
与謝蕪村(よさ ぶそん)
春の海 ひねもすのたり のたりかな
→ 春の海が一日中、ゆったりしている様子をあらわしています。
小林一茶(こばやし いっさ)
やせがえる まけるな一茶 これにあり
→ 小さなカエルに「がんばれ!」とエールを送っている元気な句。
有名俳人の俳句は、「自然の見方」「気持ちの伝え方」がとても上手なので、まねして作ると勉強になります。
家族みんなで楽しめる俳句あそび
俳句は勉強だけでなく、家族みんなで楽しめるあそびにもなります。とくに週末やお休みの日に、みんなでやってみると盛り上がります!
おすすめのあそび:
-
お題カード俳句:カードに「雪」「花」「風」などのお題を書き、引いたもので一句作る
-
写俳あそび:風景写真を見て、それに合う俳句を作る(スマホの写真でもOK)
-
俳句かるた:上の句を読み、下の句を取るようにして遊ぶ
-
季語さがしゲーム:家の中や外で、季語になりそうなものを探す
俳句あそびは、子どもの言葉の力を育てるだけでなく、親子のコミュニケーションにもなります。
日々の中に「ことばで季節を楽しむ時間」を取り入れてみましょう!
まとめ
俳句は、日本の美しい四季を感じることができるすばらしい文化です。とくに小学生のうちから俳句にふれることで、言葉を大切にする気持ちや、自然を観察する力が育ちます。
この記事では、春・夏・秋・冬、そして通年使える季語をわかりやすく紹介し、それを使った俳句の作り方やノートのまとめ方まで、楽しく学べるように説明しました。また、俳句をもっと楽しむための本やアプリ、イベント、遊び方なども紹介し、家庭や学校、自由研究などいろんな場面で役立てられる内容にまとめました。
俳句は、五・七・五のリズムと季語というたった2つのルールだけで、だれでも気軽に楽しめる表現です。だからこそ、子どもたちが自由に感じたことを言葉にして、自分だけの俳句をどんどん作っていってほしいと思います。
「おもしろい!」「こんな風に感じたよ!」という気持ちを大切にしながら、俳句を通して日本の四季とことばの魅力を楽しんでくださいね。