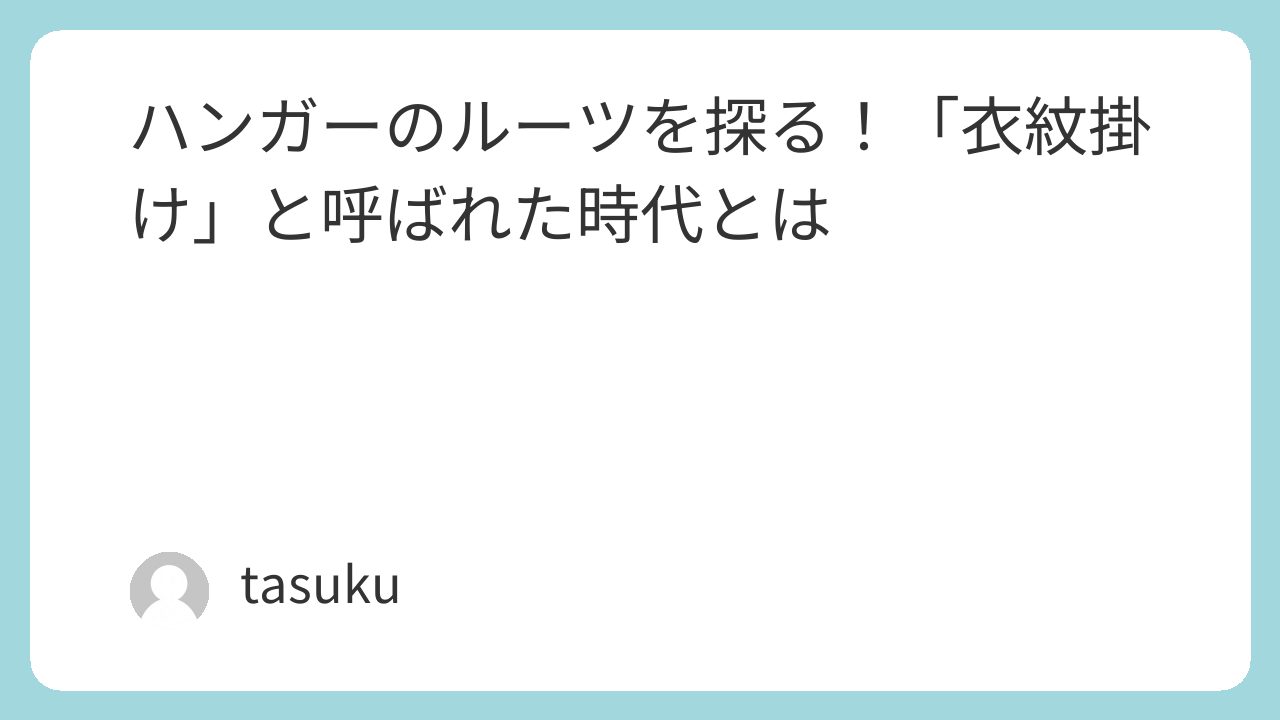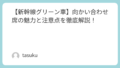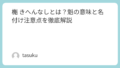普段、何気なく使っている「ハンガー」という言葉。
でも、昔の日本では違う名前で呼ばれていたって知っていましたか?
着物が主流だった時代には「衣紋掛け」と呼ばれ、暮らしの中で大切に使われてきました。
この記事では、「ハンガー」の昔の呼び方や、生活スタイルとともに変わってきた日本人の暮らしについて、わかりやすくご紹介します。
読んだあとには、身近な道具の見方がきっと変わるはずです!
\お買い物マラソン開催情報/ 楽天ランキングページはこちら<PR>
「ハンガー」の昔の呼び方とは?意外な語源と由来
衣類をかける道具のルーツ
現代で「ハンガー」と聞くと、スーツやシャツをかけるプラスチック製や木製の道具を思い浮かべる人が多いでしょう。しかし、昔の日本では洋服を吊るす文化がそもそも存在せず、「ハンガー」のような道具も一般的ではありませんでした。和服を中心とした暮らしでは、衣類は折りたたんで「箪笥(たんす)」にしまうのが基本。吊るして保管するという発想自体がほとんどなかったのです。
そんな中、明治時代の文明開化とともに洋服文化が日本に入ってきます。それにあわせて、洋服の保管方法にも変化が生まれました。最初は欧米から輸入された木製の衣類掛けが使われるようになり、これがのちに「ハンガー」と呼ばれるようになります。とはいえ、当時はまだ「ハンガー」というカタカナ語は一般には浸透しておらず、もっと和風な呼び方がされていました。
「衣紋掛け(えもんかけ)」という言葉がその代表格です。もともとは着物の襟元=衣紋を美しく整えるための棒や道具を指す言葉でしたが、洋服を吊るすための道具としても転用されるようになりました。このように、現代のハンガーのルーツには和服文化と西洋文化の融合があったのです。
和服文化と“衣紋掛け”の関係
和服を着ていた時代、日本人は洋服のように肩で服を吊るすという考え方を持っていませんでした。そのため、衣類を“掛ける”というよりも“畳んでしまう”文化が定着していたのです。しかし一方で、着物を一時的にかけておくための道具は存在しており、それが「衣紋掛け」と呼ばれていました。
衣紋掛けは木製の細長い棒の両端に脚がついた形で、着物をかけた際にシワにならないように工夫されていました。着物を脱いで一時的に保管したり、風を通したりする際に使われ、職人の手仕事によって作られた品も多く、美術品のようなものも存在しました。
特に婚礼や晴れ着などの高級な着物を扱う家庭では、衣紋掛けは必須のアイテムだったのです。また、着付けを学ぶ場などでは今でも衣紋掛けは使われています。つまり、洋服文化が浸透する以前の日本には、すでに衣類を吊るすという道具が存在していたわけですが、それは洋風の「ハンガー」とは違う思想で生まれたものでした。
衣紋掛けという言葉はその後も長らく使われ、「えもんかけ」と読み仮名を平仮名にして呼ばれることも増えていきます。この呼び方は、特に昭和の家庭やお年寄りの間ではごく自然に使われていました。
明治・大正時代に登場した言葉たち
明治維新を経て、日本は急速に西洋化の波を受けます。洋服の導入とともに、それに関わる道具や習慣も少しずつ取り入れられていきました。この時代、「ハンガー」という言葉自体はまだ日本には存在しておらず、代わりに様々な和風の呼び名が用いられていました。
例えば、「洋服掛け」や「衣類掛け」といった実用的な名称が一般的でした。また、前述の「衣紋掛け」も広く使われていた呼び名です。当時の百貨店のカタログや新聞広告を見てみると、「洋服掛け具」「洋装具」といった名称で販売されていた記録もあります。これらはどれも“外来語”ではなく、まだ日本語的な発想の範囲で名付けられていたのが特徴です。
このような言葉たちは、まだカタカナ語や英語の浸透が浅い時代だからこそ生まれた呼び方です。特に、日用品においては和風の呼び方を用いることで安心感や親しみを与えようとする流れもありました。昭和初期になってようやく「ハンガー」という言葉が徐々に市民権を得るようになっていきます。
ハンガーの語源は英語?日本語?
「ハンガー(hanger)」という言葉は、英語で“掛けるもの”という意味から来ています。英語の「hang(掛ける)」に「-er」がついて“掛けるための道具”という意味になるわけです。英語圏ではこの言葉は日常的に使われており、日本でも明治以降に英語由来の語彙として少しずつ入ってきました。
しかし、当初は「ハンガー」という言葉は一般的な日本人にはなじみが薄く、「衣紋掛け」や「洋服掛け」のような日本語で表現されていました。それでも戦後のアメリカ文化の影響や、家庭電化製品・日用品の欧米化により、「ハンガー」という呼び名が急速に広がっていきます。
特に1950年代以降のテレビCMや雑誌広告では、「ハンガー」が当たり前のように使われるようになり、英語がそのままカタカナとして定着する時代の流れを象徴しています。つまり、「ハンガー」は完全な外来語であり、日本語では「衣紋掛け」や「洋服掛け」と呼ばれていたのがその前身というわけです。
「ハンガー」と呼ばれるようになったタイミング
「ハンガー」というカタカナ語が一般家庭で使われるようになったのは、昭和30年代以降だと言われています。この頃は高度経済成長期にあたり、欧米文化が一気に日本中に広まりました。家庭の洋風化が進み、家具や収納用品も西洋スタイルにシフトしていきます。
その中で、衣類を吊るす道具として「ハンガー」が急速に普及しました。百貨店や日用品店でも“ハンガー”という名前で販売され、家庭内でも「えもんかけ」という呼び方に代わって「ハンガー」が当たり前になっていったのです。特に若い世代ではこの変化が顕著でした。
この時期にはワイヤーハンガーやプラスチックハンガーが登場し、安価で軽量な製品が大量に出回るようになりました。それも「ハンガー」という名称の浸透を後押しした要因です。こうして、長い間使われてきた「衣紋掛け」という和語は徐々に影を潜め、「ハンガー」が現代日本のスタンダードな言葉となっていったのです。
昔の日本人はどんなふうに服をかけていたのか?
和箪笥と着物収納の文化
昔の日本人は、洋服ではなく「着物」を日常着としていました。そのため、現在のように服をハンガーにかけて保管するという習慣はほとんどなく、代わりに「和箪笥(わだんす)」という収納家具を使っていました。和箪笥は引き出し式になっていて、着物をたたんで丁寧に重ねて収納することが基本です。
着物はしわになりやすく、型崩れを防ぐためにも畳み方には決まりがありました。「本畳み」と呼ばれる方法で、衿や袖、裾の折り目をそろえ、できるだけ空気が入らないように畳んで保管します。また、湿気や虫から守るために「たとう紙(文庫紙)」に包んでからしまうことも一般的でした。
このように、日本の気候や生活スタイルに合わせた収納方法が発達していたのです。和箪笥は桐材で作られることが多く、湿気に強く、防虫効果もあるため、着物の保存に適していました。地方によっては、嫁入り道具として豪華な和箪笥を持たせる風習もありました。
つまり、昔の日本人にとって「服をかける」よりも「丁寧に畳んでしまう」ことの方が一般的であり、それが日常の収納文化だったのです。
“衣桁(いこう)”と呼ばれた家具の役割
「衣桁(いこう)」とは、着物を一時的に掛けておくための木製の家具です。折りたたみ式の屏風のような形状で、広げると3面に分かれたフレームになり、上部の横棒に着物を掛けることができます。衣桁は主に寝る前や風を通すとき、または来客時に羽織をちょっと掛けておくといった場面で使われていました。
衣桁は非常に実用的でありながら、装飾性も高く、彫刻が施されたり漆塗りになっていたりと、インテリアの一部としても楽しまれていました。特に裕福な家庭では、高級な衣桁が部屋の雰囲気を引き立てる存在でもあったのです。
また、衣桁は女性が着替える際の目隠しや、着物を整える際の補助具としても活用されました。現代ではあまり見かけませんが、茶道や華道、舞踊の世界では今でも使われることがあります。着物文化と深く結びついた家具であり、「ハンガー」の役割を果たしていた日本独自の道具と言えるでしょう。
日常にあった「長押(なげし)」の使い方
日本の昔の家屋には「長押(なげし)」と呼ばれる横木が、和室の壁の上部に設置されていました。これは本来、柱と柱をつなぎ建物を補強するための構造材ですが、生活の中では“物を掛ける場所”としても活用されていたのです。
長押には「釘隠し」と呼ばれる装飾的な金具や、専用の「長押フック」が取り付けられていることが多く、そこに着物や羽織、袋物などを掛けて使っていました。これも「かける収納」の一種ですが、あくまで一時的な利用が基本で、長期保管には不向きでした。
昔の家では、来客時に脱いだ羽織を長押に掛けたり、夜に脱いだ着物を一時的に干したりするのが一般的な使い方でした。また、農作業や外出から帰った際に上着を掛けるなど、実用的な場面で活用されていたのです。
長押という建築要素が、暮らしの中で自然に“ハンガー代わり”になっていたというのは、非常に日本的な発想です。収納と建築が一体になっていたこの文化は、今の住宅にはあまり見られないスタイルですが、和の暮らしを象徴する工夫の一つでもあります。
布をたたむ文化とハンガー不要論
日本では、昔から「布を美しくたたむ」ことが文化の一部でした。風呂敷や着物、帯など、すべての布製品は丁寧にたたみ、収納するのが当たり前。こうした習慣が根付いていたため、衣類を「吊るす」発想はあまり普及しませんでした。
たとえば、着物は一度着るたびにたたんで箪笥にしまうのが基本。脱いだらすぐにきちんと畳むことが礼儀作法でもありました。布が貴重だった時代には、少しでも長持ちさせるために型崩れを防ぎ、虫や湿気から守る工夫が必要だったのです。
このような背景から、昔の日本では「吊るしておくと型崩れする」「埃がつく」「場所をとる」といった理由で、ハンガーのような道具はあまり好まれませんでした。あくまで一時的な仮置きに「衣桁」や「衣紋掛け」を使い、基本はたたんで収納するのが王道だったのです。
この“たたむ文化”は、今でもお正月や成人式、卒業式などで着物を着る際に守られています。西洋の「吊るす収納」とは対照的な、日本ならではの美意識と整理整頓の知恵が詰まった文化と言えるでしょう。
生活スタイルと収納道具の関係性
昔の日本の住まいは、部屋数が少なく、押入れや和箪笥など限られた収納スペースを有効活用する必要がありました。そのため、日常着はできるだけコンパクトに畳んで、場所を取らないようにしまうのが前提。これにより、吊るす収納よりも畳んでしまう収納が優先されたのです。
さらに、着物は季節やTPOによって使い分ける必要があり、頻繁に出し入れするわけではありませんでした。冠婚葬祭用、普段着、作業着などがそれぞれ決まった箪笥に収められていたのです。また、通気性や湿気対策として「衣替え」もきっちり行われており、定期的にたたんだ着物を虫干しする習慣もありました。
こうした生活スタイルの中で、「ハンガー」のように見える道具はあったとしても、補助的な役割にとどまり、主役になることはなかったのです。住まいの構造、家族の人数、季節感、物を大切にする心など、日本独自の生活文化が収納のスタイルを形づくっていたのです。
ハンガーの変遷とそのデザインの進化
木製ハンガーの登場とその背景
洋服文化が日本に定着し始めた明治から大正時代にかけて、最初に広まったハンガーは「木製ハンガー」でした。これらは欧米から輸入されたもので、スーツやワンピースといった新しい服の形に合わせて、肩のラインを崩さずに吊るして保管するために使われていました。
木製ハンガーは、現在と違って1本ずつ手作りされることが多く、高級感がありました。特にホテルや紳士服店では、顧客へのおもてなしや商品の美しさを保つために、丁寧に作られた厚みのある木製ハンガーが用いられていたのです。
日本国内でも、洋服の普及とともに木製ハンガーの需要が高まりました。特に洋装の広まりが進んだ昭和初期には、家具職人が家具とセットでハンガーラックや木製ハンガーを製作することもありました。また、木のぬくもりや耐久性が好まれ、家庭の中でも「衣紋掛け」の代用品として活躍するようになります。
ただし、木製ハンガーはコストがかかるため、当時の一般家庭ではまだ贅沢品でした。そのため、大切な外出着や正装用の洋服に限定して使われるケースが多かったのです。
ワイヤーハンガーが主流になった理由
戦後、日本では大量生産・大量消費の時代に突入します。その流れの中で登場したのが「ワイヤーハンガー」です。針金で作られたこのハンガーは、安価で軽く、曲げて形を整えることもできるというメリットがあり、一気に家庭やクリーニング店などで普及しました。
ワイヤーハンガーの普及には、クリーニング業界の成長が大きく関係しています。洗濯済みの洋服を掛けるために軽くて薄いハンガーが求められ、そのニーズに応えたのがワイヤーハンガーでした。クリーニング店では、使い捨て感覚で顧客に返却できるほどコストも抑えられており、その実用性は非常に高かったのです。
また、ワイヤーハンガーは重ねて収納しやすく、場所をとらないのも大きな特徴です。家庭でも洗濯後に干す際のハンガーとして重宝され、「濡れても錆びにくい加工」なども進化していきました。特に昭和30〜40年代の家庭には、必ず数本はワイヤーハンガーがあるという時代だったのです。
しかし、ワイヤーハンガーには服の形が崩れやすいという弱点もありました。そのため、より機能性を求めた進化が続いていくことになります。
プラスチック製の普及と大量生産
昭和後期から平成にかけて急速に普及したのが「プラスチック製ハンガー」です。素材が軽く、水に強く、製造コストも安いため、家庭でも店舗でも広く使われるようになりました。カラフルな色展開やさまざまな形状に加工できることから、デザイン性にも優れており、一気に主流のハンガーとなっていったのです。
プラスチック製ハンガーの登場により、用途ごとの使い分けも一般化しました。たとえば、スカート専用のクリップ付きハンガーや、ズボン用のバー付きハンガー、洗濯物用の連結型ハンガーなど、さまざまなバリエーションが生まれました。
また、百円ショップの登場によって、プラスチック製ハンガーが1本10円〜20円ほどで手に入るようになり、一般家庭でも大量に使えるようになりました。この価格革命も、普及を一気に加速させる大きな要因となりました。
さらに、成形技術の進化によって、服に跡がつきにくいデザインや、回転するフック付き、滑り止め加工のされたハンガーなど、機能面でもどんどん改良されていきます。プラスチック製ハンガーは、現代の生活における「収納ツールの主役」と言っても過言ではない存在です。
肩幅や形状の工夫、機能性の進化
ハンガーの進化は単なる素材の変化だけではありません。実は、「肩幅」や「形状」の工夫によって、服の保管方法や寿命にまで影響を与えるようになっています。たとえば、スーツやコートのような重い衣類には、肩をしっかり支える太めのハンガーが必要です。こうした専用ハンガーは、肩の丸みを保ちながら型崩れを防ぎます。
また、シャツやカットソーには、すべり止め付きのハンガーが適しています。これにより、服がずり落ちたり、襟元が伸びてしまうのを防げます。さらに、回転式フックや360度回転するタイプなど、収納の柔軟性を高める工夫も多数取り入れられています。
子ども服用の小さいサイズや、旅行用の折りたたみハンガー、さらにはアロマ機能付きや消臭素材を使ったものまで登場し、現代のハンガーは「掛ける」だけでなく、「守る」「整える」役割も担うようになっています。
こうした機能性の進化によって、ハンガーはただの道具ではなく、衣類を美しく保つためのパートナーとして重要な存在になっています。
現代のハンガーは“滑らない”がキーワード
ここ最近、最も注目を集めているのが「滑らないハンガー」です。これまでのハンガーでは、肩がツルツルしていて服がずり落ちてしまう、という悩みを持つ人が多くいました。特に素材が滑りやすいシルクやニットなどの衣類では、何度も落ちてしまってイライラするという声が多かったのです。
そんな中、登場したのが「ノンスリップハンガー(滑らないハンガー)」です。表面にベルベットのような起毛素材が使われていたり、特殊なゴム加工が施されていたりと、衣類がしっかり固定される工夫がされています。見た目もスリムでおしゃれなデザインが多く、SNSや収納系YouTubeでも紹介され、話題となりました。
特に「MAWAハンガー」などの海外ブランドは、その滑らなさとスタイリッシュなデザインで人気を集め、日本でも爆発的に売れました。また、100円ショップや無印良品、ニトリなどもそれぞれ独自の「滑らないハンガー」を展開しており、選択肢が豊富になっています。
現代では「収納効率」「衣類を守る」「見た目もスマート」がハンガー選びのポイントになっており、まさに日常の中の“進化する道具”となっているのです。
昭和・平成の家庭で使われていた“呼び方”あれこれ
「衣紋掛け」と「えもんかけ」の違い
「衣紋掛け(えもんかけ)」という言葉は、着物文化が根付いていた時代から使われてきた伝統的な呼び名です。もともとは、着物を着るときや脱いだときに一時的に掛けておくための木製の棒や台のことを指していました。格式ある場面では今でも使われており、たとえば結婚式の衣装合わせや、茶道・日本舞踊の舞台裏などで目にすることができます。
昭和の家庭では、この「衣紋掛け」という言葉が日常的に使われていましたが、やがて口語では「えもんかけ」と柔らかい音に変化していきます。どちらも同じ意味を持ちますが、前者がやや正式・書き言葉的、後者は口語・会話の中で自然に使われるようになったのです。
この「えもんかけ」は、ハンガーのことを指す一般的な言葉として、特に昭和の主婦や高齢者の間で多く使われました。昭和30年代生まれの方にとっては「洋服をえもんかけにかけておきなさい」という表現はごく自然なものであり、親や祖父母世代の影響で今でも使う人がいます。
つまり、「衣紋掛け」=和語・伝統、「えもんかけ」=口語化・日常語として、同じ語源を持ちながら時代に応じて形を変えた、日本語らしい言葉の変化だと言えるでしょう。
地域による呼び方のバリエーション
ハンガーや衣紋掛けには、地域ごとに独特な呼び方が存在していました。たとえば関西地方では「えもんかけ」が一般的に使われており、京都や大阪では年配の方が今でもこの呼び方を使うことがあります。一方、関東では「ハンガー」という言い方がやや早く普及したとされ、地域による言葉の差がはっきりと見られました。
また、九州や四国地方では「服かけ」「洋服掛け」など、より機能的な表現が使われるケースもあります。中には「服掛(ふくかけ)」や「かけもん」という方言的な呼び方も残っており、昔ながらの言葉の豊かさを感じさせます。
こうした呼び方の違いは、方言や地域の文化によるものであり、世代が変わるごとに徐々に「ハンガー」へと統一されていきましたが、祖父母の家に行ったときなどに聞くと懐かしく感じる人も多いはずです。
今ではあまり耳にしなくなった呼び方ですが、地方に根付いた生活文化の中には、こうした古い名称がまだ息づいており、地域の暮らしや価値観を映し出す貴重な文化資源とも言えるでしょう。
昭和の家庭用品カタログにみる呼称
昭和時代には、家庭用品や生活雑貨が掲載された分厚い通販カタログや新聞の折り込みチラシが各家庭に配布されていました。これらの紙媒体をひもとくと、「ハンガー」という言葉よりも「洋服掛け」「衣類掛け」「衣紋掛け」という表現がよく使われていたことがわかります。
たとえば昭和40年代の主婦向けカタログでは、「衣類整理に便利な洋服掛け」「木製衣紋掛け台付き」「ワイヤー洋服掛け10本セット」といった商品名が並び、英語の“ハンガー”という表現は目立ちませんでした。これは、当時の日本人がまだ和語に親しみを持ち、家庭の中でも英語を使う機会が少なかったことを物語っています。
また、昭和のホームドラマや雑誌広告でも「えもんかけ」は頻繁に登場しており、家族の会話の中でも自然に使われていました。このように、メディアや商品名の中にその時代の言葉遣いが色濃く反映されているのです。
カタログや広告は、当時の生活スタイルや価値観を知るための貴重な資料です。現在の「ハンガー」に統一される以前には、さまざまな表現が存在し、人々がどんなふうに暮らしの道具と向き合っていたかが読み取れます。
CMや広告で使われた言葉たち
昭和〜平成初期のテレビCMや新聞広告にも、「ハンガー」ではなく「衣紋掛け」や「洋服掛け」といった表現がよく使われていました。これは、当時の広告業界が“わかりやすく、親しみやすく”を重視していたためで、特に主婦層や高齢者をターゲットとした商品では、カタカナ語よりも和語を選ぶ傾向があったのです。
たとえば、洗濯用ハンガーのCMでは「ぬれても安心、強化プラスチック製えもんかけ!」といったナレーションが使われていましたし、収納家具のチラシでも「木製洋服掛け台」や「回転式衣紋掛けスタンド」など、具体的な名前で呼ばれていました。
一方で、平成に入ると徐々に「ハンガー」という表現も登場し始め、若年層向けの商品やインポートブランドの広告では“オシャレ”なイメージを前面に押し出すために、カタカナ語が好まれるようになっていきました。
この変化は、言葉の選び方によってターゲット層の印象が変わることを示しており、言語と広告の関係性を知る上でも興味深い要素です。
家庭の中でのおばあちゃんの言葉遣い
「えもんかけ、ちゃんと元の場所に戻しときなさいよ」——こんなセリフを、昔おばあちゃんに言われたことがある人も多いのではないでしょうか。昭和から平成にかけて、お年寄りの世代では「ハンガー」よりも「えもんかけ」という呼び名が主流でした。
特に着物をよく着ていた世代にとって、「えもん(衣紋)」という言葉には特別な意味があり、着物の衿元を整えること、そして着物を丁寧に扱うことの象徴でした。だからこそ、ハンガーのような日常的な道具にも「えもんかけ」という名前が自然に使われていたのです。
家庭内では「お父さんの上着はえもんかけに」「濡れたものは別のえもんかけに掛けときなさい」といった具合に、家族全体でこの言葉が通じていた時代がありました。それは単なる言葉以上に、“物を大切にする”という考え方や“きちんと整える”という日本的な価値観を含んだ文化だったのです。
時代が変わり、若い世代では「ハンガー」が当たり前になった今でも、家庭の中でふと耳にする「えもんかけ」という言葉には、どこか温かく懐かしい響きがあります。
ハンガーとは何かを考える:言葉が教えてくれる日本の暮らし
外来語としての定着と文化の融合
「ハンガー」という言葉は、もともと英語の「hanger」から来た外来語です。しかし、日本に入ってきた当初は誰もがすぐに使いこなせたわけではなく、昭和の中頃までは「衣紋掛け」や「洋服掛け」という和風の言葉が根強く使われていました。それが徐々に変化し、「ハンガー」という呼び名が自然に使われるようになったのは、日本人の生活が洋風化し、文化そのものが融合していった証拠でもあります。
昭和の高度経済成長とともに、日本人の暮らしは大きく変化しました。和室から洋室へ、和服から洋服へとライフスタイルが変わる中で、言葉も変化していきます。「ハンガー」はその象徴的な存在です。道具の呼び方一つとっても、そこには時代背景や文化の変遷が色濃く表れているのです。
今では、ほとんどの人が「ハンガー」という言葉を違和感なく使っていますが、その裏には日本語と外来語の融合という長い歴史があります。外来語をそのまま取り入れつつも、自分たちの生活に合う形で使いこなしていく。それが日本語の面白さであり、言葉の進化の魅力でもあります。
日本語と英語の混在する日用品
現代の生活では、日用品の多くにカタカナ語が使われています。ハンガーもその一つですが、他にも「ドライヤー」「トースター」「クッション」「テーブル」など、家庭の中には英語を基にした名称があふれています。これらの言葉は、生活に必要な道具が外国から入ってきたと同時に、そのまま名前も一緒に定着していったケースが多いのです。
一方で、日本語の名前も残っています。たとえば「お玉(おたま)」や「茶碗(ちゃわん)」「すり鉢」「ざる」など、和の生活道具に関しては昔からの言葉が今でもしっかり使われています。つまり、現代の日本の暮らしは、英語と日本語、どちらの言葉も共存する非常にユニークな言語空間になっているのです。
このような混在は決して悪いことではなく、それぞれの文化や使い方に合わせて自然に選ばれていることの証です。ハンガーもまた、「衣紋掛け」としての顔と「hanger」としての顔の両方を持っている、言葉の交差点に立つ存在と言えるでしょう。
昔の言葉が残る場面と消えゆく言葉
「えもんかけ」や「衣紋掛け」という昔ながらの言葉は、今ではあまり日常会話で使われなくなりました。しかし、完全に消えてしまったわけではありません。たとえば、着物文化が残る茶道や能、日本舞踊の世界、あるいは旅館や伝統行事の現場では、今でも「衣紋掛け」という言葉が自然に使われています。
また、家庭の中でも高齢者が使う言葉として、孫世代に引き継がれることもあります。「これ、えもんかけにかけといて」と言われて、最初はピンと来なかったけれど、使っていくうちに覚えていくというケースも少なくありません。こうして、昔の言葉が“家族の中での記憶”として残っていくのも、とても日本らしい言葉の伝わり方です。
ただし、社会全体としては「ハンガー」に一本化されつつあり、「えもんかけ」は少しずつ姿を消しつつあります。言葉は時代とともに変わるもの。だからこそ、残っている昔の言葉に出会うと、どこか懐かしく、温かい気持ちになるのです。
生活スタイルとともに変化する道具の名前
生活が変われば、使う道具も変わり、呼び方も自然と変わっていきます。たとえば、かつては「冷水筒(れいすいとう)」と呼ばれていたものが今では「ピッチャー」と呼ばれ、「電気洗濯機」は「洗濯機」、「アイロン掛け台」は「アイロン台」に。どれも生活の変化とともに、名称が短く・覚えやすくなり、時代に合った形に進化しています。
ハンガーもまさにそのひとつ。「衣紋掛け」という丁寧で格式ある名前から、「えもんかけ」という親しみやすい口語へ、さらに「ハンガー」という現代的な呼び名へと変わってきました。この変化には、衣類の形の変化、住居の洋風化、そして収納スタイルの合理化などが影響しています。
つまり、道具の名前の変化は、暮らしの変化そのもの。私たちがどんな暮らしをしてきたのか、これからどんな暮らしをしていくのか。それを映し出す鏡のような存在なのです。言葉の変化を追うことで、社会の姿まで見えてくるのが日本語の面白さでもあります。
懐かしい言葉に触れることで得られる温かさ
昔使っていた言葉をふと耳にしたとき、不思議と心がほっとすることがあります。「えもんかけ」もそのひとつ。おばあちゃんやお母さんが日常的に使っていたその響きには、昭和の家庭のぬくもりや、丁寧な暮らしの記憶が詰まっています。
今は便利で効率的な暮らしが当たり前になりましたが、どこかで「ものを大切にする」「丁寧に暮らす」といった昔の考え方が恋しくなることもあります。そんなとき、懐かしい言葉に触れることで、心の中にある“日本人らしさ”を思い出すことができるのです。
また、こうした言葉は親から子へ、祖父母から孫へと自然に伝わっていくものでもあります。日々の暮らしの中で、「これ、えもんかけに掛けといて」なんて一言を交わすことで、言葉と一緒に思い出も残っていく。それが日本語の持つ、言葉以上の価値なのかもしれません。
まとめ
「ハンガー」という言葉ひとつを取っても、日本の暮らしや文化の変遷が色濃く映し出されていることがわかりました。もともとは着物文化に根付く「衣紋掛け」から始まり、生活スタイルの変化とともに「えもんかけ」という親しみやすい呼び方へ、そして昭和後期から平成にかけて「ハンガー」という外来語が一般化していきました。
収納方法も、畳んでしまう和の文化から、洋服を吊るして保管するスタイルへと大きく変わりました。道具そのものも、木製からワイヤー、プラスチック、そして滑らない高機能タイプへと進化を遂げ、今では生活に欠かせない存在となっています。
しかし、こうした便利さの陰で、昔ながらの言葉や習慣が静かに姿を消していることも事実です。懐かしい呼び方に触れることで、私たちは改めて日本の丁寧な暮らしぶりや物を大切にする心を思い出すことができます。
ハンガーひとつを通して見える日本の暮らしの歴史、そして言葉の温かさ。これからも、そんな小さな文化を大切にしていきたいですね。