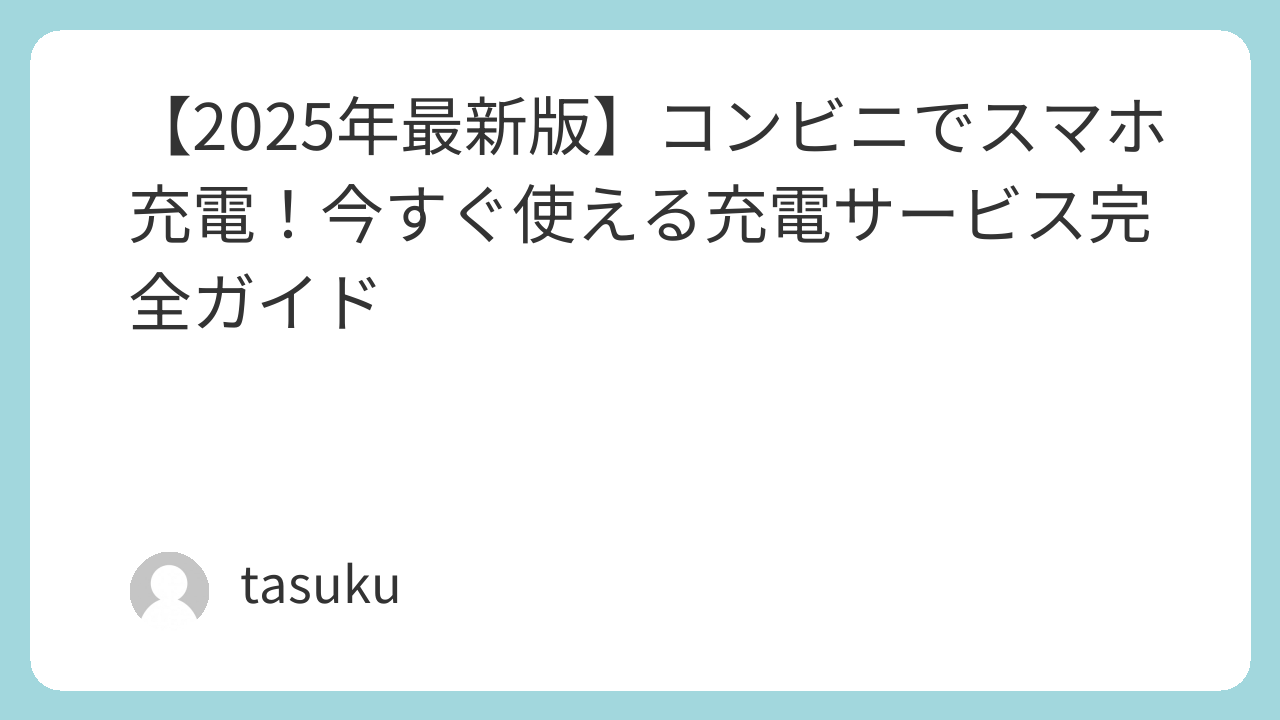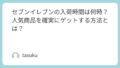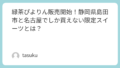スマホのバッテリーが突然ゼロに…そんな時、あなたはどうしますか?
実は今、コンビニで携帯をサクッと充電できる時代になっています。知らなきゃ損する最新の充電サービスや、レンタルバッテリーの仕組み、注意点まで徹底解説!この記事を読めば、もうスマホの電池切れで困ることはありません。
\お買い物マラソン開催情報/ 楽天ランキングページはこちら<PR>
コンビニで携帯充電ができるって知ってた?基本情報と利用のコツ
なぜ今コンビニでの充電が注目されているのか
現代人にとってスマホは生活の必需品です。連絡手段、ナビ、決済、SNS、情報収集とあらゆる場面で使われており、バッテリーが切れると大きな不便が生じます。そんな中、注目されているのが「コンビニでの携帯充電サービス」です。以前は充電器を自宅に忘れたらアウトでしたが、今では出先でも気軽に充電できる環境が整ってきました。
特に都市部では、仕事や学校帰りに立ち寄れるコンビニで充電できるのは非常に便利です。また、災害時や緊急時にもコンビニが「ライフライン」の一部として機能するようになっており、スマホの充電設備もその一環です。
さらに、最近ではレンタル型モバイルバッテリーの普及により、「自分の充電ケーブルがなくても」「スマホを置いていくだけで」充電が可能になり、利便性が格段に向上しています。こうした背景から、コンビニでの携帯充電は今、必要不可欠なサービスとして注目されているのです。
コンビニ充電スポットの種類と設置場所
コンビニで利用できる充電サービスには、大きく分けて2種類あります。1つ目は「備え付け充電器タイプ」、2つ目は「モバイルバッテリー貸出タイプ」です。
備え付けタイプは、レジ横やコピー機の近く、イートインスペースなどに設置されており、スマホを直接接続して充電します。主にiPhone用Lightningケーブル、Android用USB-CやmicroUSBケーブルが完備されており、幅広い機種に対応しています。
一方、モバイルバッテリー貸出タイプは、スマホアプリを使ってレンタルし、使い終わったら別のコンビニや駅、カフェなどで返却できる「シェアリング型」です。これにより、自分の行動に合わせて柔軟にバッテリーを使えるのがメリットです。
設置場所は店舗ごとに異なりますが、見つけ方としては「ChargeSPOT」や「mocha」などの専用アプリで検索するとすぐに判明します。最近ではコンビニの公式アプリでも充電スポット情報を確認できるようになってきています。
主要コンビニ別の充電サービス(セブン・ローソン・ファミマなど)
日本の三大コンビニチェーンであるセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートは、それぞれ異なる形で携帯充電サービスを提供しています。
セブンイレブンでは、一部店舗に「ChargeSPOT」が設置されており、スマホアプリからモバイルバッテリーを簡単に借りることができます。セブンカフェの横やATM付近にあることが多いです。
ローソンも「ChargeSPOT」または「mocha」のバッテリースタンドを導入しています。ローソンの場合、Loppi端末と連携したり、ローソンアプリでの支払いにも対応している店舗が増えています。
ファミリーマートでは、独自の端末または「ChargeSPOT」が設置されている店舗が多く、近年はファミマWi-Fiとの併用で快適なモバイル体験を提供しています。
各チェーンで対応アプリや利用方法が異なるため、事前に確認しておくとスムーズに使えます。公式アプリに情報が掲載されていることも多いので、ダウンロードしておくと便利です。
料金相場と支払い方法はどうなってる?
コンビニでの携帯充電サービスの料金相場は、タイプによって異なります。
備え付け型の充電ステーションの場合、15分〜30分で100円前後というのが一般的です。長時間の利用が想定されないため、短時間で安価に充電したい方に向いています。
一方、モバイルバッテリーのレンタルサービス(例:ChargeSPOT)では、最初の30分で165円、その後6時間以内で330円といったプランが主流です。24時間までの利用もでき、料金は時間に応じて変動します。
支払い方法は現金以外にも、クレジットカード、PayPay、LINE Pay、楽天ペイ、Apple Payなど、キャッシュレス決済が主流になっています。専用アプリを通して支払う形式のものが多いため、スマホにあらかじめインストールしておくのがおすすめです。
このように、自分の充電ニーズに合わせて最適なプランと支払い方法を選ぶことが重要です。
こんなときに便利!利用シーン別活用法
コンビニ充電は、さまざまなシーンで役立ちます。
たとえば通勤・通学中にスマホのバッテリーが切れそうなとき。駅近のコンビニでモバイルバッテリーを借りれば、移動中でも安心です。また、観光中に地図アプリやカメラを使いすぎて電池が減ったときにも、充電スポットがあると非常に助かります。
夜遅くまで営業しているコンビニなら、終電を逃したときの緊急対応にも役立ちます。スマホのバッテリーがなくなれば、タクシーも呼べません。そんなとき、近くのコンビニで数分充電するだけで、大きな安心につながります。
また、災害時や停電時にも、コンビニの電源とモバイルバッテリーは重要なライフラインになります。定期的に利用方法を確認しておくことで、いざというときに慌てず対応できます。
モバイルバッテリーのレンタルが便利!「ChargeSPOT」などの人気サービスを解説
レンタルバッテリーの仕組みってどうなってるの?
モバイルバッテリーのレンタルサービスは、スマホのバッテリーが切れそうなときに、コンビニや駅、カフェなどに設置されたスタンドからバッテリーを借りて使うという仕組みです。代表的なサービスには「ChargeSPOT」「mocha」「RentaCharge」などがあります。
利用方法はとても簡単。まず、専用のスマホアプリをダウンロードし、地図から近くのバッテリースタンドを探します。目的のスタンドが見つかったら、アプリでQRコードを読み取り、バッテリーを取り出して使用します。
バッテリーにはiPhone用のLightning、Android用のUSB-CとmicroUSBの3種類のケーブルがついているので、どんなスマホでも基本的に対応可能。返却は借りた場所に戻す必要はなく、全国の対応スタンドならどこでも返せるのが大きな魅力です。
このサービスは、スマホ充電が生活インフラの一部となった今、急速に広まっています。駅、空港、ショッピングモール、そしてもちろんコンビニにも設置されていて、いざという時にとても心強い存在です。
全国のコンビニに設置中!対応店舗の見つけ方
モバイルバッテリーのレンタルスタンドは、全国の多くのコンビニで導入されています。特にセブンイレブン、ローソン、ファミリーマートの主要チェーンでは導入が進んでおり、都市部では駅前のほとんどのコンビニに設置されていると言っても過言ではありません。
店舗を探すには、各サービスが提供しているスマホアプリを活用するのが便利です。「ChargeSPOT」のアプリでは、現在地周辺のレンタル可能なスタンドを地図で表示でき、バッテリーの在庫数まで確認可能です。「mocha」なども同様に検索機能があり、初めてでも迷わず利用できます。
また、Googleマップなどで「モバイルバッテリーレンタル」と検索するだけでも、設置されているコンビニを見つけやすくなっています。最近では、店舗のガラスに「ChargeSPOT設置店」などのステッカーが貼られていることも多いので、目印にすると良いでしょう。
料金体系と時間ごとの比較
レンタルモバイルバッテリーの料金体系は、時間ごとに決まっているのが一般的です。以下に、主要なサービスの料金を比較表でまとめてみましょう。
| サービス名 | 30分以内 | 6時間以内 | 24時間以内 | 返却期限超過(1日あたり) |
|---|---|---|---|---|
| ChargeSPOT | 165円 | 330円 | 528円 | +330円/日(最大3,300円) |
| mocha | 150円 | 300円 | 500円 | +300円/日 |
| RentaCharge | 200円 | 350円 | 550円 | +300円/日 |
このように、短時間の利用なら200円以下で済むケースがほとんどです。出張や観光などで外出時間が長くなる場合は、24時間プランを選んでもワンコイン程度で済みます。注意点としては、返却し忘れると追加料金が発生するため、利用後はなるべく早く返却するのがおすすめです。
また、一部のキャンペーン時には無料または割引クーポンが配布されていることもあるので、アプリの通知はこまめにチェックしておきましょう。
アプリの使い方を画像付きでわかりやすく
アプリの使い方はとても簡単。ここでは「ChargeSPOT」を例に、基本的な流れを説明します。
-
アプリをダウンロード
App StoreまたはGoogle Playから「ChargeSPOT」アプリをダウンロードします。 -
アカウントを作成(またはログイン)
電話番号やメールアドレスで登録し、ログインします。 -
現在地周辺のスタンドを検索
地図が表示されるので、近くのコンビニを選択。バッテリーの空き状況も確認できます。 -
QRコードを読み取る
選んだスタンドの端末に表示されているQRコードをアプリで読み取ります。 -
バッテリーが取り出される
端末から自動でバッテリーが出てくるので、それを取り出してスマホに接続します。 -
返却は別のスタンドでもOK
アプリで返却可能な場所を確認し、空きスロットのあるスタンドに戻すだけで完了。
直感的な操作で使えるため、機械が苦手な人でも安心して利用できます。画像付きマニュアルはアプリ内でも閲覧可能なので、困ったときは参照してみましょう。
レンタルと購入、どっちがお得?
「モバイルバッテリーは買った方がいいのか、それとも借りた方が得なのか?」という疑問は、多くの人が抱えるテーマです。どちらがお得かは、使用頻度やライフスタイルによって変わります。
たとえば、毎日スマホを外で多用し、電池切れになることが多い人は、3,000円〜5,000円程度で購入できる高性能なバッテリーを持っていた方が長期的にコストを抑えられます。また、複数デバイスを同時に充電できるモデルもあり、非常に便利です。
一方で、たまにしか充電が必要にならない人や、荷物を増やしたくない人にはレンタルが最適です。特に旅行中や緊急時など「今だけ必要」というシーンでは、レンタルの手軽さが魅力です。
また、バッテリーは数年使うと劣化するため、管理が面倒な人にもレンタルは向いています。「買うほどじゃないけど、たまに使う」──そんな人にはコンビニレンタルがぴったりの選択肢です。
急いでるときこそ要注意!コンビニ充電の落とし穴
充電器が使えない時間帯があるって本当?
意外と知られていませんが、コンビニに設置されている充電器やレンタルスタンドは、24時間いつでも使えるわけではありません。特に都市部以外の店舗やフランチャイズ店では、深夜時間帯にサービスを一時停止しているケースがあります。これはセキュリティ対策や、清掃・メンテナンスのためです。
また、レンタル型バッテリースタンドは、スタッフが手動で再起動や管理をしている場合もあり、システムの不具合で一時的に利用できないこともあります。店舗によっては「充電サービスは○時〜○時まで」と書かれた張り紙があることも。
さらに、深夜帯は充電スタンドにバッテリーが戻っておらず、「貸出中」の状態が続いていることも少なくありません。アプリでは「在庫あり」と表示されていても、実際には使えないこともあるため、注意が必要です。
どうしても深夜に充電したい場合は、事前にアプリで複数店舗の在庫を確認するか、代替手段(駅やカフェ、ホテルなど)を用意しておくと安心です。
スマホの種類によっては充電できないことも
すべてのスマホが、コンビニの充電サービスに対応しているわけではありません。たとえば、**USB-Cポートのないガラケーや、特殊な機種(ゲーミングスマホ・海外製スマホなど)**は対応ケーブルがなく、充電できない可能性があります。
また、最近はMagSafe対応のiPhoneや、Qi規格のワイヤレス充電のみで運用している人も増えています。コンビニの有線充電器では対応していないことが多く、その場合は別途変換アダプターが必要になります。
さらに、保護ケースを付けたままだと、ケーブルが奥まで差し込めない場合もあるため、取り外しが必要になることも。特にバッテリー一体型ケースや分厚いケースは要注意です。
レンタル型バッテリーには3つのケーブルが内蔵されていますが、それでも全機種対応とは限りません。利用前に、自分のスマホに合ったケーブルが含まれているか確認する癖をつけましょう。
盗難やデータ流出のリスクは?
コンビニでスマホを充電する際、注意しなければならないのがセキュリティ面です。充電ケーブルに見せかけた「データ転送機能付きケーブル」を使うと、スマホ内のデータが抜き取られる「ジュースジャッキング」と呼ばれる被害が発生する可能性があります。
現在のコンビニ充電器の多くは、電源供給専用のケーブルを使っており、通常はデータ転送が無効になっていますが、100%安全とは言い切れません。また、モバイルバッテリーも中身が改造されていたり、偽装品が混在するリスクがあります。
公共の場でスマホを置きっぱなしにするのも非常に危険です。特に充電中にその場を離れるのは盗難のリスクが高まります。万が一スマホが盗まれた場合、LINE、SNS、決済アプリが不正に使われる可能性もあるため、「顔認証」「指紋認証」や「パスコードロック」は必須です。
できれば自分の持ち物から充電するのが一番安全。どうしても外部の充電設備を使う場合は、目を離さずに、信頼できる場所で短時間だけ利用するようにしましょう。
過充電によるスマホ故障の可能性
スマホのバッテリーは「リチウムイオン電池」が使われており、過充電によって劣化や膨張、発熱などのトラブルを引き起こすことがあります。特に、長時間の充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が縮まりやすくなります。
一部の古いコンビニ充電器は、満充電になっても電力供給を停止せずに流し続けてしまうことがあります。最近のスマホは過充電防止機能を備えていますが、機種や設定によっては効果が限定的な場合もあります。
また、夏場の車中や屋外など高温環境で充電すると、バッテリー温度が上昇してしまい、最悪の場合、発火や爆発の危険も否定できません。実際にバッテリー膨張によるスマホ爆発の事例は国内外で報告されています。
安心して使うには、短時間・短時間の充電をこまめに行うのがベストです。80%程度で充電をストップするよう心がけると、バッテリー寿命を長持ちさせることができます。
安全に使うための5つのチェックポイント
最後に、コンビニでの充電を安心・安全に使うためのチェックポイントを5つご紹介します。
-
充電器の状態を確認する
コードが断線していないか、端子がサビていないかチェック。異常があれば使用を避けましょう。 -
自分のスマホに合った端子を使う
iPhone、Androidで端子が異なるため、誤って差し込むと破損の原因になります。 -
充電中は目を離さない
盗難やトラブル防止のため、絶対にスマホを放置しないようにしましょう。 -
短時間利用を心がける
過充電を防ぐためにも、10〜30分の充電で切り上げるのが理想です。 -
不具合があったら店員に報告する
壊れている充電器を放置すると、他の利用者にも被害が及ぶ可能性があります。
これらのポイントを意識するだけで、トラブルを未然に防ぎ、安心してコンビニ充電を活用できます。
コンビニでスマホ充電できないときの対処法まとめ
店舗に充電器がない!そんなときの対応策
出先で「コンビニに行けば充電できる」と思って入ったのに、充電器が設置されていない…そんな経験はありませんか?実際、すべてのコンビニに充電設備があるわけではありません。特に地方の小規模店舗や、フランチャイズ店では設置していない場合もあります。
そんなときは、まず近隣の別のコンビニ店舗を探すのが基本です。「ChargeSPOT」などのアプリを使えば、周辺にバッテリースタンドがある店舗をすぐに検索できます。Googleマップで「モバイルバッテリー」「充電 スポット」と検索してみるのもおすすめです。
また、店舗に充電器がなくても、店員さんに聞いてみると「レジ裏で貸し出しできる充電器」や「販売しているモバイルバッテリー」があるケースもあります。特にファミリーマートやローソンでは、モバイルバッテリーをレジ横で販売していることがよくあります。
外出先での充電トラブルに備えて、スマホに「周辺施設の検索アプリ」を入れておくと、いざという時にとても便利です。
モバイルバッテリーを持っていない人のための緊急対策
モバイルバッテリーを持っておらず、かつ近くに充電設備もない場合は、限られたスマホの電池をできるだけ長く使う工夫が必要です。まず最初に行いたいのが、スマホの省電力モードの起動です。
iPhoneなら「低電力モード」、Androidなら「バッテリーセーバー」などの機能が用意されており、画面の明るさ、バックグラウンド動作、位置情報などを制限してバッテリーの持ちを延ばすことができます。
また、Wi-FiやBluetooth、位置情報(GPS)などもオフにすると、さらに効果的です。通知や自動同期も一時的に止めることで、バッテリーの無駄な消費を減らせます。
不要なアプリは閉じ、使用は最小限にとどめましょう。どうしても連絡が必要な場合は、LINEの「低データモード」や音声通話のみの使用に切り替えるのもひとつの手です。
駅やカフェの充電スポットを使う方法
コンビニ以外にも、スマホ充電ができるスポットは意外と多くあります。まず挙げられるのが「駅構内の充電ブース」です。特にJRの主要駅や私鉄のターミナル駅では、カフェ併設型や専用の充電カウンターが整備されています。
また、カフェやファストフード店(例:スターバックス、マクドナルド、ドトールなど)では、コンセントやUSBポート付きの座席が設けられていることが多く、飲食すれば自由に使えるのが魅力です。
ショッピングモールや家電量販店(ビックカメラ、ヨドバシカメラ)などでも「充電ステーション」や「休憩所に設置されたUSBポート」がある場所があります。
これらの施設は、アプリ「ChargeSPOT」「Japan Connected-free Wi-Fi」「駅すぱあと」などで検索可能なので、事前に確認しておくと安心です。
近くのレンタル充電スポットの探し方
バッテリーが少ない状態で、近くのレンタルスポットを探すのは焦りますよね。そんな時に頼りになるのが、ChargeSPOTの専用アプリです。このアプリは、GPSと連動して現在地周辺のスタンドをリアルタイムで表示してくれるうえ、バッテリーの在庫状況まで確認できます。
操作もシンプルで、アプリを開く→地図表示→ピンをタップ→スタンド情報をチェック→QRコードで借りる、という流れです。表示にはおおよその距離やルートも示されるので、移動の目安にもなります。
ほかにも、「mocha」「RentaCharge」「充レン(じゅうれん)」など複数のサービスがあるため、念のため複数アプリをインストールしておくとさらに安心です。
また、全国対応のバッテリースタンドは「借りた場所以外でも返却可能」なので、帰宅途中や職場付近で返却すればOK。利便性の高さはピカイチです。
スマホのバッテリーを節約する裏技集
最後に、スマホのバッテリーを節約する裏技をいくつかご紹介します。
-
画面の明るさを手動で最小限に
自動調整ではなく、手動で暗く設定することでバッテリーの消費が抑えられます。 -
ダークモードを活用
特に有機EL(OLED)ディスプレイを搭載しているスマホでは、黒色表示が多いほど電力消費が少なくなります。 -
通知・バイブレーションをオフにする
振動機能は意外と電力を消費します。通知も必要最低限にしましょう。 -
不要なアプリのバックグラウンド動作を停止
設定からアプリごとに通信制限ができる場合もあるので、不要なものはオフに。 -
位置情報を一時停止
ナビや地図アプリを使っていないときはGPSをオフにすると長持ちします。
これらの工夫を組み合わせれば、数%のバッテリーでも数時間持たせることが可能です。覚えておくと、いざというときに役立ちます。
未来の充電スタイルはこう変わる!コンビニ充電の次の一手
非接触ワイヤレス充電の導入は進んでいる?
非接触でスマホを充電できる「ワイヤレス充電」は、ここ数年で急速に普及しています。iPhoneでは8以降のモデル、Androidでも多くのハイエンド機種がこの機能に対応しています。充電パッドにスマホを置くだけという手軽さから、自宅だけでなく公共スペースでも導入が進んでいます。
実は、一部のコンビニでもワイヤレス充電器の導入が始まっています。特にイートインスペースのある店舗では、テーブルにワイヤレス充電パッドを埋め込む形で設置されていることがあり、買い物ついでにコーヒーを飲みながら充電できる仕組みが整いつつあります。
また、今後はスマート家具との連動や、待ち時間の長い施設(病院、空港、銀行など)でもこの技術が活躍するでしょう。ワイヤレス充電の利点は「ケーブルいらず」であること。コンビニ利用者にとっては、手ぶらで立ち寄っても充電できる便利さが魅力です。
ただし、現時点ではまだ導入店舗数が少なく、エリアに偏りがあるため、今後の普及拡大に期待が集まっています。
ソーラー型・自動販売機連動型など新サービスの紹介
技術の進化により、コンビニ充電の未来はさらにユニークになっていくと考えられます。その一例が**「ソーラー充電スタンド」や「自動販売機連動型充電器」**です。
ソーラー充電スタンドは、太陽光で発電した電力を使ってスマホを充電する仕組みで、環境にやさしい点が注目されています。特に災害時や停電時でも使える「独立型スタンド」として、地方自治体と連携した試験導入が進んでいます。
また、最近話題になっているのが「自動販売機連動型充電器」です。これはジュースやコーヒーを買うついでに、横に設置されたUSBポートやワイヤレスパッドでスマホを充電できるという画期的なシステム。すでに都内の一部駅や商業施設で導入されており、今後はコンビニ併設型の自販機にも広がる見込みです。
これらの新サービスは、SDGsにも貢献する“サステナブル”な側面もあるため、環境意識の高まりと共に今後一層注目されていくでしょう。
海外と日本のコンビニ充電サービスの違い
実は、日本のコンビニ充電サービスは海外と比べて「非常に発達している」と言われています。たとえばアメリカでは、コンビニに充電サービスがあるケースはほとんどなく、代わりにカフェや大型商業施設に集中しています。
中国や韓国では、日本と同じようにモバイルバッテリーのレンタルが盛んですが、決済や借り方がQRコードや顔認証による完全自動化されているのが特徴です。また、バッテリー自体も超高速充電タイプが多く、5分で50%以上充電できるモデルも存在します。
一方、日本ではセキュリティ性と信頼性が重視されており、店舗スタッフが常駐し、トラブル対応も可能な体制が整っています。これは海外ではあまり見られない日本ならではの安心感と言えるでしょう。
今後、日本のサービスも自動化や高速化の面で進化し、よりグローバルなスタンダードに近づいていくと予想されます。
SDGsとコンビニ充電の関係
SDGs(持続可能な開発目標)の観点からも、コンビニの充電サービスは重要な役割を果たし始めています。特に「エネルギーをみんなに そしてクリーンに(目標7)」「産業と技術革新の基盤をつくろう(目標9)」「住み続けられるまちづくりを(目標11)」などに関連しています。
たとえば、再生可能エネルギーを活用した充電スタンドの導入や、モバイルバッテリーの再利用・リサイクル促進などは、環境負荷の低減に貢献します。
また、高齢者や子どもなど、スマホがライフラインになるユーザー層に対して、誰もが使える充電インフラを整備することは「社会的包摂(インクルージョン)」の視点からも価値があります。
今後、各コンビニチェーンが環境への取り組みを加速させる中で、充電サービスの進化がSDGs達成にどう寄与していくのかにも注目が集まるでしょう。
これからのライフスタイルに必要な「充電リテラシー」
今やスマホの充電は、単なる便利機能ではなく「生活インフラの一部」として認識されつつあります。だからこそ、私たちには正しい知識と行動、いわば**「充電リテラシー」**が求められています。
たとえば「バッテリーをゼロにしてから充電するのは良くない」「100%にするより80%で止めた方が長持ちする」「安物の充電器は発火リスクがある」など、知っておくべき情報は数多くあります。
また、公共の充電スポットを使うときのマナーや、混雑時に譲り合う心も現代社会には不可欠です。特に災害時や緊急時に、スマホをいかに効率的に使い続けるかは、命を守る手段にも直結します。
今後は学校や企業、地域活動などで「スマホ充電の正しい使い方」を学ぶ機会が増えていくかもしれません。そうした時代に備えて、日頃から意識しておくことが、これからのスマートな生活の鍵になるでしょう。
【まとめ】コンビニでの携帯充電は「今や生活インフラ」のひとつに
この記事では、「コンビニでの携帯充電」をテーマに、基本的な使い方からモバイルバッテリーのレンタルサービス、注意すべき落とし穴、緊急時の対処法、そして未来の充電スタイルまで、幅広く解説してきました。
スマホが欠かせない現代社会において、充電の確保は“電気のある生活”と同じくらい重要になっています。特に、いつでも立ち寄れるコンビニで手軽にスマホを充電できるサービスは、生活の安心感を高めてくれる存在です。
ChargeSPOTなどのシェア型サービスの普及、非接触型のワイヤレス充電、さらにはソーラーやSDGsへの貢献など、「コンビニ × 充電」の進化は今後も止まりません。
しかし、便利さの裏にはセキュリティ面や対応機種の制限、過充電リスクといった落とし穴もあります。**「充電リテラシー」**をしっかり身につけ、安全に賢くサービスを使うことがこれからの新常識です。
出先でも、旅行中でも、災害時でも、コンビニ充電サービスはきっとあなたの強い味方になってくれるはず。この記事が、あなたの“いざという時”の安心材料になれば幸いです。