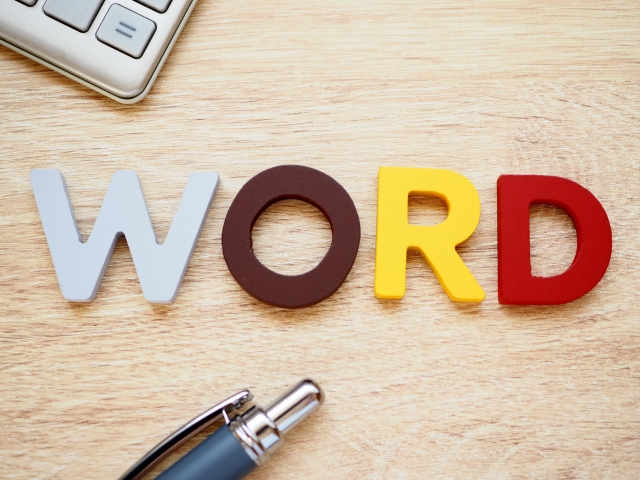「七(なな・しち)」って、どっちで読むのが正しいの?と迷ったことはありませんか。
電話番号では「なな」と言うのに、「七時」は「しちじ」と読むなど、日本語の「七」は場面によって読み方が変わります。
この記事では、そんなややこしい「七」の読み方について、音読み・訓読みの基本から、名詞・助数詞ごとの使い分け、さらには方言までをやさしく解説します。
NHKの基準や文化的な背景も踏まえて紹介するので、この記事を読めばもう「七」の読み方で迷わなくなるはずです。
日本語を正しく、美しく使いたい方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
七の読み方は「なな」と「しち」どっち?基本ルールを整理
「七」は日本語で二通りの読み方を持つ、ちょっとややこしい数字です。
日常会話では「なな」と読むことが多いですが、学校や職場で時間を言うときは「しちじ」と言いますよね。
ここでは、まずその基本ルールをしっかり整理しておきましょう。
「七」は音読みと訓読みの両方がある
日本語の漢字には「音読み」と「訓読み」があります。
音読みは中国から入ってきた読み方、訓読みは日本独自の読み方のことです。
「七」の場合、音読みがしち、訓読みがななです。
つまり、「なな」も「しち」もどちらも正しい読みなんですね。
「なな」と「しち」はどちらも正解
NHKの「ことばのハンドブック」では、数を単体で読むときの基準を次のように示しています。
| 数字 | 標準の読み方 | 許容される読み |
|---|---|---|
| 4 | よん | し |
| 7 | なな | しち |
| 9 | きゅう | く |
この表を見ると、4・7・9は訓読みが標準とされていることがわかります。
ただし、後ろに名詞や助数詞がつくと、読み方が変わることもあるんです。
数字として読むときの基本的な使い分け
単独で数を言うときは「なな」が基本です。
たとえば電話番号や暗証番号を伝えるとき、「しち」と言うと「いち」や「し」と聞き間違われることがあるためです。
一方で、「七時」や「七月」のように時間や月を表す言葉では、「しち」を使うのが自然です。
つまり、聞き取りやすさ重視なら「なな」、慣例重視なら「しち」と覚えておくと便利です。
| 状況 | おすすめの読み方 |
|---|---|
| 数字を単独で言う(電話番号・暗証番号など) | なな |
| 時間・月などの慣用表現 | しち |
| 助数詞がつくとき | 文脈によって変化 |
「なな」と読むケース|日常会話・助数詞・名詞の例
ここでは、「七」を「なな」と読む代表的なケースを整理します。
普段の会話や文章で最もよく使われるパターンなので、まずはここからしっかり押さえておきましょう。
「なな」が優先される理由
「なな」は訓読みであり、日本語の中でより自然に響く発音です。
特に、助数詞(枚、行、回など)と組み合わせるときは、「しち」よりも発音しやすく聞き取りやすいのが特徴です。
そのため、誤解や聞き間違いを防ぐ目的で「なな」が選ばれることが多いのです。
「七行」「七枚」など、ななと読む主な言葉一覧
次の表は、「なな」と読むのが一般的な名詞・助数詞の例です。
| 言葉 | 読み方 | 備考 |
|---|---|---|
| 七行 | ななぎょう | 文や詩などの行数を数えるとき |
| 七枚 | ななまい | 紙や皿など薄い物を数えるとき |
| 七回 | ななかい | 繰り返しの回数 |
| 七段 | ななだん | 階段や級位などの段数 |
| 七度 | ななど | 温度・角度など |
| 七名 | ななめい | 人数を数えるとき(フォーマルでない場合) |
このように、形のある物や回数などを数えるときは「なな」を使うのが自然です。
数字や助数詞と組み合わせるときのコツ
基本的に、助数詞の頭が濁音(だ・ば・が)や破裂音(ぱ・た・か)で始まるときは、「なな」と読むほうが発音しやすいです。
たとえば、「七番(ななばん)」「七杯(ななはい)」などがそうですね。
一方、「七人(しちにん)」のように、歴史的な慣用で「しち」が固定化されている言葉もあります。
判断に迷ったときは、言いやすさと一般的な慣例の両方を考えるのがコツです。
| 語尾のタイプ | おすすめの読み方 | 例 |
|---|---|---|
| 濁音・破裂音で始まる助数詞 | なな | ななばん・ななはい・ななだん |
| 慣用化した名詞 | しち | しちにん・しちじ |
こうして見てみると、「なな」は使い勝手がよく、発音のトラブルも少ない万能な読み方といえます。
日常会話ではまず「なな」を使うと覚えておくと安心です。
「しち」と読むケース|時間・年月・行事の例
次に、「七」を「しち」と読むケースを整理していきましょう。
「しち」は音読みであり、フォーマルな文脈や慣用表現で使われることが多い読み方です。
ここでは、時間や月、行事など、日常の中でよく出てくる「しち」の使い方を中心に紹介します。
「しち」が使われる場面の特徴
「しち」は、もともと中国語由来の読み方で、数を含む熟語や正式な言葉で多く使われます。
そのため、公式・公的な文脈では「しち」を優先するのが一般的です。
また、発音の流れがスムーズで、漢語のリズムと合いやすいのも特徴です。
「七時」「七月」「七福神」などの読み方例
代表的な「しち」読みの言葉を一覧にまとめました。
| 言葉 | 読み方 | 解説 |
|---|---|---|
| 七時 | しちじ | 時間を表す場合に使用。ナナジとは言わない。 |
| 七月 | しちがつ | 月の名前として定着している。 |
| 七人 | しちにん | 人を数える場合、慣用的に「しち」。 |
| 七年 | しちねん | 年数・期間を表すときの正式な読み。 |
| 七回忌 | しちかいき | 仏教用語として伝統的に定着している。 |
| 七福神 | しちふくじん | 「福」を重ねた縁起の良い言葉。 |
このように、「時間」「月」「行事」「年数」などのカテゴリーでは、「しち」が自然に選ばれます。
特に宗教的・文化的な表現では、「しち」で読むことが伝統的なマナーでもあります。
「しち」と読むときに注意すべき聞き間違いポイント
ただし、「しち」は「いち」や「し」と音が似ているため、聞き間違いが起こりやすいという弱点もあります。
そのため、電話で「7時に集合」と伝えるときなどは、「ななじ」と言い換えることもあります。
つまり、発音の明瞭さを優先する場面では「なな」、慣用的な表現では「しち」と使い分けるのが正解です。
| 場面 | おすすめの読み方 | 理由 |
|---|---|---|
| フォーマルな文書・公式発言 | しち | 慣例的で標準的な発音 |
| 会話・電話などの口頭説明 | なな | 聞き間違いを防ぐため |
「しち」は正式で格調高い印象を与えますが、日常では柔軟な使い分けが求められます。
—
どっちでも読める?「なな」「しち」両方ありの言葉
ここでは、「なな」でも「しち」でも通じる、少しややこしいパターンを見ていきます。
どちらかが間違いというわけではなく、場面によって自然な読み方が変わるのが特徴です。
「七年」「七人」など、どちらの読みも使われる場合
次のような言葉は、「なな」と「しち」のどちらでも使われることがあります。
| 言葉 | 読み方 | 使われ方の傾向 |
|---|---|---|
| 七年 | ななねん/しちねん | 会話では「ななねん」、正式表現では「しちねん」 |
| 七人 | ななにん/しちにん | 人数を強調するときは「しちにん」 |
| 七回 | ななかい/しちかい | 日常会話では「ななかい」 |
| 七年生 | ななねんせい/しちねんせい | 教育制度によって変化 |
このように、同じ言葉でも使う文脈や目的によって自然な読み方が異なります。
会話では言いやすさを重視し、文書では伝統的な読み方を採用する傾向があります。
状況によって読み方が変わる理由
なぜ読み方が変わるのかというと、日本語の柔軟さと聞き取りやすさのバランスが関係しています。
もともと「七」は「しち」が正式でしたが、「いち」「し」と混同されやすいことから、発音の明瞭な「なな」が広まったのです。
つまり、どちらが正しいかではなく、「どうすれば誤解なく伝わるか」が重要なのです。
会話で迷ったときの判断基準
次のような判断基準を意識しておくと、迷わず使い分けられます。
| 判断基準 | 選ぶ読み方 | 具体例 |
|---|---|---|
| 正式な文書・ニュース・式典 | しち | 七回忌、七月、七時 |
| 日常会話・口頭での伝達 | なな | 七回、七年、七人 |
| 発音の明瞭さを重視したいとき | なな | 電話番号・暗証番号など |
「どちらでもOK、でも使う場面で選ぶ」という意識を持つと、自然な日本語が使えるようになります。
地方によって違う?方言での読み方の豆知識
ここからは少しマニアックな話題として、「七」の読み方に関する方言の違いを紹介します。
全国的には「なな」または「しち」が一般的ですが、地方によっては意外な発音をする地域もあるんです。
愛媛や九州では「ひち」と読む地域も
愛媛県をはじめ、西日本の一部地域では「七(しち)」をひちと発音する方言が残っています。
たとえば、数字を数えるときに「いち、に、さん、し、ご、ろく、ひち、はち、く、じゅう」と言う人が多いんです。
これは昔の日本語における発音変化の名残で、古語では「し」が「ひ」に変化することがよくありました。
| 地域 | 発音 | 特徴 |
|---|---|---|
| 愛媛県・高知県 | ひち | 7をひちと発音。西日本特有の古い音変化。 |
| 九州地方 | ひち/しち | 年配層に「ひち」派が多い。 |
| 東日本 | しち/なな | 標準語に近い発音が主流。 |
この「ひち」という発音は、今ではあまり聞かれなくなりましたが、地域の言葉文化として大切にされています。
まるで方言が「日本語のタイムカプセル」みたいですね。
方言が生まれた背景と歴史的な由来
昔の日本語では、「し」や「す」の音が「ひ」「ふ」に近い発音で使われていたといわれています。
そのため、「しち」は自然と「ひち」に変化し、それが地域ごとに定着したのです。
方言の違いは単なる言葉の違いではなく、地域の歴史や文化の証拠でもあるというわけです。
| 時代 | 変化の傾向 | 例 |
|---|---|---|
| 奈良時代〜平安時代 | 「し」「す」→「ひ」「ふ」 | しち→ひち、すし→ふし(例外あり) |
| 江戸時代以降 | 標準語化が進行 | 「ひち」→「しち」へ統一 |
方言を知ることで、日本語という言葉の奥深さを改めて感じられますね。
「七」のつく言葉まとめ|知っておきたい慣用句・文化表現
最後に、「七」を含む日本語の言葉や慣用句をまとめて紹介します。
ここでは、「なな」と読むもの、「しち」と読むものの両方を見ながら、その背景や意味を理解していきましょう。
「七転び八起き」「七草」など「なな」と読む言葉
「なな」と読む言葉には、日本独自の文化や生活に根ざしたものが多いです。
七色(なないろ)、七草(ななくさ)、七転び八起き(ななころびやおき)などが代表的です。
これらは「繰り返し」「多様性」「幸運」などの前向きな意味を持つことが多いんです。
| 言葉 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| 七色 | なないろ | 多様な色、豊かな変化のたとえ。 |
| 七草 | ななくさ | 春の七草を指す。無病息災を願う風習。 |
| 七転び八起き | ななころびやおき | 何度倒れても立ち上がるたとえ。 |
| 七不思議 | ななふしぎ | 不可思議な出来事や伝説を数える表現。 |
| 七十路 | ななそじ | 70歳の別称。 |
どれも日本文化の中で古くから親しまれている言葉ばかりです。
「七五三」「七輪」など「しち」と読む言葉
一方、「しち」と読む言葉には、伝統行事や宗教的な意味を持つものが多いです。
| 言葉 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| 七五三 | しちごさん | 子どもの成長を祝う行事。 |
| 七輪 | しちりん | 炭火を使う日本独自の調理器具。 |
| 七福神 | しちふくじん | 幸福をもたらす七柱の神々。 |
| 七変化 | しちへんげ | さまざまに姿を変えることのたとえ。 |
| 七回忌 | しちかいき | 仏教で亡くなって7年目の法要。 |
「しち」で読む言葉は、伝統や信仰と深く結びついているのが特徴です。
言葉そのものが日本人の文化的な感性を映しているようですね。
読み方が例外的な言葉リスト
中には、読みがどちらにも当てはまらない、特殊な慣用表現もあります。
| 言葉 | 読み方 | 備考 |
|---|---|---|
| 七夕 | たなばた | 古語由来の特殊読み。 |
| 七宝焼 | しっぽうやき | 音便化による変化。 |
| 七曜 | しちよう/ななよう | 両方の読み方が併存。 |
このような例は、日本語がいかに柔軟で、歴史的な経緯を引き継いでいるかを示しています。
一見不規則に見えても、文化や発音の流れには必ず理由があるんです。
まとめ|「七」は文脈で読み分けるのが正解
ここまで、「七(なな/しち)」の読み方や使い分けを詳しく見てきました。
最後に、この記事のポイントを整理しておきましょう。
「なな」と「しち」どちらも日本語として正しい読み方
まず大前提として、「なな」と「しち」はどちらも正しい読み方です。
「なな」は訓読みで日本語らしい響きがあり、日常会話や助数詞との組み合わせで使われます。
一方、「しち」は音読みで、時間・月・行事などの正式表現に使われることが多いです。
どちらが正しいかではなく、どんな場面で使うかが大事ということですね。
| 読み方 | 主な使用シーン | 例 |
|---|---|---|
| なな | 日常会話・聞き間違いを避けたい場面 | ななかい・ななばん・ななまい |
| しち | 時間・年月・正式表現・慣用句 | しちじ・しちがつ・しちふくじん |
迷ったときの実践的な判断法
会話の中で迷ったときは、次の2つを意識すればOKです。
- 聞き取りやすさを重視 → 「なな」
- 慣習・形式を重視 → 「しち」
たとえば、数字を読み上げるときや電話での会話では「なな」が安全です。
逆に、文章やニュース、行事名などでは「しち」を使うと自然になります。
日本語の奥深さを感じる「七」という漢字
「七」という漢字一つをとっても、読み方や文化の広がりがとても豊かです。
地域によって「ひち」と読む方言があったり、「七夕(たなばた)」のように特殊な読みが残っていたりと、日本語の多様性を感じます。
つまり、「七」をどう読むかは、その場の目的や伝えたい相手次第なんです。
文脈に合わせて自然に使い分けることが、正しい日本語の第一歩といえるでしょう。