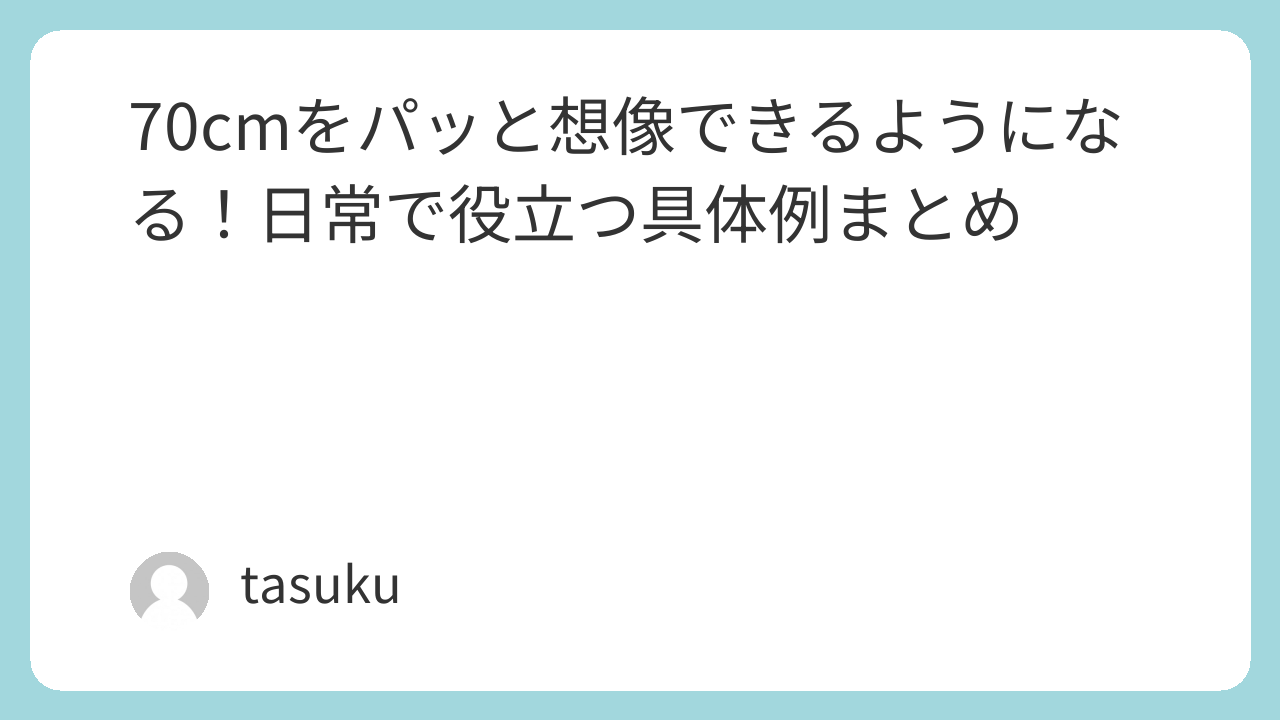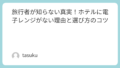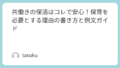「70cmって、実際どのくらいの長さ?」
そう思ったことはありませんか?普段あまり意識しない単位ですが、家具や洋服、子どもの成長、ペットグッズなど、意外とよく出てくる長さなんです。この記事では、70cmをわかりやすくイメージできるように、身近なものとの比較や、実際に測るコツまでやさしく解説します。数字だけではピンとこないあなたにも、「なるほど、そういうことか!」と納得してもらえるはずです。
\お買い物マラソン開催情報/ 楽天ランキングページはこちら<PR>
70cmはどんな長さ?イメージしにくい理由とは
70cmは普段の生活でよく使う単位?
70cmという長さ、実は日常生活ではそこまで頻繁に使わない中途半端なサイズかもしれません。たとえば「1メートル」や「50cm」はよく耳にしますが、70cmって具体的にどのくらい?と聞かれてパッと答えられる人は少ないのではないでしょうか。学校で長さの単位を学んでも、実際に70cmという長さを目にする機会は意外と限られています。そのため、頭の中でピンとこないという人も多いんです。
人によって「長い・短い」の感覚が違う理由
人が「長い」と感じるか「短い」と思うかは、その人が普段どんなものを基準にしているかによって変わります。たとえば、小さな子どもにとっての70cmは「とても長いもの」ですが、大人にとっては「まあまあ短い」と感じるかもしれません。身長、日常で使う道具、職業など、生活スタイルによって感じ方に差があるのです。これが、長さの感覚が人それぞれ違う理由なんですね。
長さの感覚を育てることの大切さ
小さいうちから長さの感覚を身につけることは、生活の中でとても役立ちます。たとえば、家具の配置や衣類のサイズ、料理での計量など、すべて「なんとなくの感覚」が頼りになります。この感覚は訓練によって育てることができるんです。70cmをイメージできるようになるだけで、身の回りのものの大きさもよりリアルに想像できるようになりますよ。
70cmを実際に測ってみよう
一番確実なのは、実際に70cmを測ってみることです。定規があれば2本つなげればOKですし、メジャーや巻尺を使えば一発で確認できます。手元にそうした道具がなければ、スマホアプリのARメジャー機能を使っても簡単です。目で見て、手で感じることで、70cmという長さが一気に「体にしみこむ」ようになります。
なぜ70cmという長さが気になるのか
検索などで「70cmどのくらい?」と調べる人が多いのは、それだけ気になる場面が多いということです。たとえば、家具の寸法、スーツケースのサイズ、洋服の丈、子どもの成長など。具体的に生活の中で「これってどのくらい?」と知りたくなるシーンで、70cmという数字が登場することが多いんです。そんなときに、この記事が「なるほど、そういうことか!」という気づきのきっかけになればうれしいです。
身近なもので70cmをイメージしよう!
A4コピー用紙との比較
A4サイズのコピー用紙は、縦が約29.7cm。これを2枚縦に並べると、だいたい59.4cmになります。そこにさらに3分の1枚(約10cm)を足すと、ちょうど70cmくらいになります。つまり、A4の紙2枚と少し分ということですね。これはとても身近で、学校や職場、家庭にもあるものなので、実際に並べてみると「なるほど、これくらいか」とすぐにわかります。
子どもや動物のサイズに例えると?
小学校低学年の子ども(6〜7歳)の身長は、平均で110〜120cmほどです。その子がしゃがんだり座ったりしたときの高さが、ちょうど70cm前後になります。また、犬でいえば中型犬の柴犬やビーグルなどが、体長でおおよそ70cm前後です。ペットを飼っている方なら、「うちの子と同じくらいか!」とイメージしやすいですね。
家の中にある70cm前後のもの
家の中を見回してみると、意外と70cm前後のものは多くあります。たとえば、リビングのローテーブルの高さ、キッチンのカウンターの高さ、テレビ台の幅など。IKEAやニトリの商品サイズにも70cmという寸法はよく登場します。家具選びの際にも「70cmくらいならこのスペースに入るかな?」と考えることが多いですね。
スマホやリモコンを重ねると?
スマートフォンの平均的な長さは15cmほど。これを5台分縦に重ねると、ちょうど75cmくらいになるので、スマホ5台=約70cmと覚えておくと便利です。テレビのリモコンもだいたい20cm前後なので、3〜4本並べると70cmくらいになります。こうした「手元にあるもので試す」という方法も、長さをつかむのにとても効果的です。
旅行カバン・スーツケースのサイズ感
飛行機の預け荷物用スーツケースの中型サイズがちょうど70cmくらいの高さです。空港で見かける「あのサイズ感」が70cmと覚えておくと、イメージしやすくなります。また、キャリーバッグやキャスター付きのトランクなども、サイズ表記に「高さ70cm」とあると、1〜2泊用よりはちょっと大きめのサイズだな、と判断できますね。
70cmを他の単位に変換してみよう
メートルやミリメートルでの比較
まず、センチメートル(cm)を他のメジャーな長さの単位に変換してみましょう。70cmは、0.7メートル(m)です。1メートルは100cmなので、単純に100で割ればOKですね。ミリメートル(mm)では700mmになります。1cm=10mmなので、70×10=700という計算です。数字だけ見ると少し大きく感じますが、あくまで単位の違いで、実際の長さは変わりません。単位を変えると感覚が変わることもあるので、状況によって使い分けると便利です。
インチに変換するとどうなる?
日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが、海外では「インチ(inch)」という単位がよく使われます。1インチは約2.54cmなので、70cmをインチに直すには、70÷2.54で計算します。すると約27.56インチ。パソコンモニターやテレビ画面のサイズでよく見かける数字ですね。「27インチのディスプレイ」と聞くと、70cmくらいなんだなと理解できるようになります。ちなみに、テレビの27インチは対角線の長さですが、幅の目安としても役立ちます。
足(フィート)やヤードとの関係
さらに、フィート(feet)やヤード(yard)という単位もあります。これも海外、特にアメリカやイギリスでよく使われる単位です。1フィートは約30.48cmなので、70cmは約2.3フィートです。また、1ヤードは約91.44cmなので、70cmは約0.77ヤードになります。こうした単位も、スポーツ(アメリカンフットボールやゴルフなど)で目にすることがあるので、知っておくとちょっと得した気分になれますね。
体感できる長さに直すには?
数字だけではピンとこないこともありますよね。そんなときは、実際に体を使って体感するのが一番です。たとえば、腕を肩の高さで真横に広げたときの手首から肘までが、大人でおよそ30〜35cmほど。これを2回分と少しと考えると、70cmに近づきます。こうした「自分の体」を使った長さの基準を持っておくと、どんな場面でも「だいたいこれくらいかな?」と判断できるようになります。
定規や巻尺を使って測るポイント
一番正確なのはやっぱり道具を使って測ることです。定規で70cm測る場合、30cm定規なら2本以上必要なのでちょっと面倒。そこで便利なのが、**巻尺(メジャー)**です。裁縫用のソフトタイプやDIY用の金属メジャーが家にあると、長さを簡単に測れます。また、最近ではスマホにAR(拡張現実)機能を使った「メジャーアプリ」もあるので、これを使えばスムーズに測定できます。道具を活用することで、誤差の少ない測定が可能になりますよ。
シチュエーション別!70cmが役立つ場面
家具を買うときのサイズ確認
インテリアや家具選びの際、サイズ確認はとても重要です。たとえば、「この棚、70cmの幅があるけど、部屋に置けるかな?」といった判断が必要になることもあります。一般的なテレビ台やサイドテーブル、カラーボックスなどは、幅や高さが70cm前後のものが多くあります。部屋のスペースを考えるうえで、70cmがどのくらいのサイズかを体感的に理解していると、失敗しない家具選びができるようになります。特に賃貸住宅などでスペースが限られている場合は、「あと10cm大きかったら入らなかった…!」ということもあるので要注意です。
洋服やスカート丈の感覚
洋服の丈の長さを選ぶときにも、70cmという数字がよく登場します。たとえば、スカートの丈が70cmだと、身長160cm前後の人であれば膝下10cmほどの**ミモレ丈(ふくらはぎの中間)**になります。これは上品で大人っぽい印象を与える丈として人気です。また、ワンピースの総丈やコートの着丈なども、70cm台が基準になることが多いです。「70cmの丈って、着るとこれくらいの長さなんだ」と把握していると、通販での服選びがとてもスムーズになります。
ペットのゲージやリードの長さ
ペット用品でも70cmという長さはよく使われます。たとえば、猫用や小型犬用のゲージの横幅が70cm前後のものは多く、部屋に置く場所の目安になります。また、犬のリード(引き綱)も短めタイプであれば70cm〜100cmが主流です。狭い場所や電車・バスなど公共の場面で使う場合、70cmのリードならコントロールしやすく安全です。実際に使ってみると、「これくらいの距離なら安心して歩けるな」と納得できる長さになります。
ベビーグッズや育児用品選び
赤ちゃん用のベビーグッズにも、70cmというサイズが登場します。たとえば、70cmサイズのベビー服は、生後6ヶ月〜1歳ごろの赤ちゃんが着られるサイズです。また、おむつ替え用マットやプレイマットなども、70cm×70cmくらいの正方形がよくあります。育児中は、赤ちゃんを寝かせたり、抱っこしたりする場面で「どのくらいのスペースが必要か?」がとても重要になるため、70cmの感覚を知っておくと便利です。
DIYや引っ越しでのメジャー活用術
DIYや引っ越しの際にも、70cmという長さが基準になることがよくあります。たとえば、壁に棚をつける、カーテンレールを設置する、段ボール箱を積み上げるなど、「どのくらいの長さが必要か?」という場面で活躍します。市販の収納ボックスやラックも、横幅70cmのものが多く、荷造りや配置を考える際に便利です。事前に70cmの紙やヒモを用意しておくと、スムーズにサイズ確認ができて時短にもなります。
実際に70cmを測ってみよう!おすすめの方法と注意点
家にあるもので代用するアイデア
「メジャーがない!」「定規も見つからない!」というときでも、70cmをおおよそ測る方法はいくつかあります。たとえば、**A4コピー用紙(縦 約30cm)**を2枚並べて、さらにもう1枚を3分の1にカットして追加すれば、約70cmになります。また、靴のサイズを活用する方法もあります。27cmの靴を2足半分並べると、だいたい70cm。こうした身近なものを使えば、目安として十分な長さを測れます。お子さんと一緒に長さの学習を兼ねてやってみるのも楽しいですよ。
スマホアプリで簡単に測る方法
最近はスマートフォンに搭載されている「ARメジャー」アプリを使えば、カメラ越しに長さを測ることができます。iPhoneであれば標準アプリ「計測」がそれに該当し、AndroidでもGoogleの「Measure」アプリなどがあります。使い方はシンプルで、画面上で測定したい2点をタップするだけ。もちろん厳密な誤差はあるものの、おおまかな長さを知るには十分便利です。特に外出先やすぐに測りたいときには重宝します。
紙・ヒモ・タオルでカンタン測定
他にも、紐(ひも)やリボン、タオルなどを使って長さを目印として記録する方法もおすすめです。たとえば、長めのタオルを使って70cmのところに印をつけておけば、次回以降も簡単に再利用できます。紙を長く切っておいて、70cmで折り曲げておくのも便利です。これらは軽くて扱いやすく、子どもや高齢者でも簡単に測れるため、誰でも手軽に使える方法として重宝します。
外で測るときのコツ
屋外で長さを測りたいときは、風や地面のデコボコなどで測定が難しくなることがあります。そういうときは、地面にチョークやマスキングテープなどで「スタート」と「ゴール」の位置を明確にするのがコツです。また、紐や棒を使って目印をつけておけば、簡単に測ることができます。ベンチや道路標識など、すでに存在する物を目安にしても良いでしょう。ただし、公園や公共の場では周囲への配慮も忘れずに。
誤差をなくすためのチェックポイント
測定するときに大切なのが、「なるべくまっすぐに測る」ことです。定規や巻尺が曲がっていたり、斜めになっていると、思ったより短く(または長く)測ってしまうことがあります。また、布や紐で測るときも、たるみや伸びに注意しましょう。きちんと張った状態で印をつけるのがコツです。スマホアプリを使う場合も、カメラの角度を正面にして、測りたい場所に対して平行になるように意識するだけで、誤差を減らせます。
まとめ
70cmという長さは、一見すると中途半端でイメージしづらい数字かもしれません。しかし、この記事を通じて見てきたように、私たちの生活の中には70cmに関係する場面が意外と多く存在します。A4用紙の長さ、スーツケースのサイズ、子どもの身長、ペット用品、洋服の丈、家具の寸法など、さまざまな場面で「70cmくらいってどのくらい?」という疑問が生まれます。
大切なのは、数字だけでなく具体的なイメージに結びつけることです。実際に測ってみたり、身近なもので例えたりすることで、感覚的に「このくらいだな」とわかるようになります。これができるようになると、通販、家具選び、育児やペット用品選び、さらにはDIYや引っ越しの場面まで、あらゆる判断がぐっとラクになります。
70cmをしっかりイメージできるようになることは、日常生活での小さなストレスやミスを防ぐ力にもつながります。この記事が、あなたの「長さの感覚」を育てるヒントになれば嬉しいです。